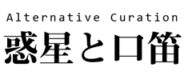当たりまえのことですが、最初から大人として生まれてきた者はいません。
ではわれわれはいつ子供でなくなったのでしょう。いつ大人になったのでしょうか。大人になった者はいったいどこにいるのでしょう。
ワーズワースはかつて詩のなかで、子供はその人間の親だという意味のことを述べました。子供のころの経験、それはたしかに人の方向を決め、あるときは助け、あるときは挫きます。
本書に集められた歓び、驚異、孤独、不安、恐怖は、多くの人間が共有するものです。けれども不思議なことにそこにはなぜか明確な個人性もあります。見事に普遍なものと独自なものが共存しているように見えます。
おそらくここに集められた優れた文章は読者の心に鮮やかに子供時代を蘇らせます。濃密なノスタルジーを見ることもできますが、それはある種の錯覚でしょう。われわれはおそらく子供時代を失ってはいません。違います。子供時代はつねに心の奥のほうでそのままつづいています。われわれはみな大きな子供なのです。
本書は〈ナショナル・エッセイ・プロジェクト〉の一冊目です。叢書名はポール・オースターの出版企画「ナショナル・ストーリー・プロジェクト」から直接的に借用したものです。
400字詰め原稿用紙換算約240枚。価格800円。
作品抜粋
砂鉄 斎藤真理子
星座には線が引いてあると思っていた。図鑑や子供用百科事典で見た通りに。線が引かれた星座を実際に見たことはなかったが、たまたまお天気が合ってなかったのだろう、出来の悪い日に夜空を見たのだろうと思っていた。
あるとき、そんな線はないと知った。
だめだ。
世界、本気ではない。
とうっすら思ったが、気持ちは隠した。
山の話 夏野雨
父から墓の話を聞いてから、私は急に裏山を意識するようになった。私の部屋は二階で、北向き、つまり山側にあった。窓は西と北にあり、寝台に寝そべって足元の窓を覗くと、西向きの窓から、ちょうどお墓があったらしきなだらかな斜面が見える。そこは周囲を竹に囲まれた日当たりのいい場所で、春には蕗や筍が生え、一家の食卓を豊かにしてくれていた。もしかすると長年埋まっていたご先祖さまの栄養があったがゆえに、いろんなものが育ったのかもしれない。私もどうせいつか死ぬならあの細長いロッカーのような厨子の一つに納まるのではなく、そのまま裏山に埋まって山の栄養になったほうがいいな、と、ぼんやりと考えていた。
PS41 宮内悠介
高学年になると、給食や弁当のほかにアウトランチというものが許された。親から三ドルくらいをもらって外食してもよいというものだ。おのずと、皆、いかに食費を切りつめて駄菓子を買うかに腐心した。ピザ屋で巨大なピザの一切れとスプライトを買って二ドルくらい。残る一ドルで菓子を買うということが多かった。もう少し切りつめると漫画も買える。でもぼくは小さなスケートボードの玩具がついてくる食玩が好きで、色とりどりのスケートボードを好んで集めていた。
幼年期の始まり 川合大祐
などと言う話はどうでも良かった。まあそういう土着信仰を取り入れつつ、いちおう耶蘇であるから、赤い屋根の教会があった。あの鋭角的な、きっと今なら小さく見える建築物は、限りなく巨大なものに見えた。灰色の髪と青い目をした、西洋人の神父さんが住んでいたのだが、ほとんど姿を見せたことがない。だから、園児たちに宗教的な橋渡しをする役目は、もっぱらシスターたちが担っていた。
祭りの記憶 北原尚彦
わたしは女の子の次に、そのくじ引きをやることにした。
くじを引き、女の子の真似をして手のひらを振り、再挑戦を要求する。
それを何度も繰り返す。
何回目だかにわたしが手を振ると、屋台の男性――若かったか年寄りだったかは覚えていないが大人の男性だったのは確か――が言った。
「あんた、まだ続けられるほど金を持ってるのかい」
わたしは衝撃を受けた。「やり直し」は最初の代金での権利ではなく、ただ何回もくじを引かされていただけだったのだ。そして、引いた回数分の代金を、後から要求されるのだ。
プラスティックの宝石箱 mayumiNightly
私の乗ったブランコは弟の前だけれど、後ろのブランコとはかなり距離がある。やがてけたたましくブザーが鳴ってゆっくりと動き出すブランコ。賑やかな今でいうとエレクトリック昭和風?な音楽が楽し気に鳴り始める。
楽しくワクワクする気持ち、がしかし、ワクワクしたのは最初の数秒だけでそれはどんどん想像を超えた高さになり、遠心力もあったから私は心底怖くなった。
私は大丈夫、じっとしていれば落ちる事はない、でも三歳の小さい弟は……。
弟の乗った後ろのブランコが心配で気が気でなく、風と遠心力はボサボサ髪を更にボサボサにして私は何度も振り返って九歳の精いっぱいの声で叫んでいた。
わたしのヒーロー Pippo
その年の夏、ひょんなことからラッキィ池田の誕生日(十月二十五日)を知り、「そうだ! 帽子を作って誕生日プレゼントに贈ろう」と不意に思い立った。調べたら、ラッキィの所属する事務所の住所が判明したので、そこへ送ればきっと本人へ届くだろう、と幼心に算段をつけた。
東京―一九七〇年代の子ども時代 三月の水
学校の一番近くに住んでいた加藤くんは自分の部屋を持ちステレオも置いてあったから、毎日のようにみんなで帰りに寄った。ビートルズを初めて聴いたのもそこでのこと。そのうちに彼の家は、各々が買ったLPを持ち寄り、聴きくらべ、交換する場所となっていく。スティービー・ワンダー、エルトン・ジョン、ピンク・フロイドなどなど。
当時、LPは二千円、中学生の小遣いは一月千円だったから、ラジオで聴いては、慎重に、そして重複しないように購入し、貸し借り、ときには交換をしたものだった。
そこにはみじかい光があって 桐谷麻ゆき
空の広い、大きな川と中くらいの川がぶつかる街に住んでいたころ、ひとつ年上のお兄ちゃんは秘密基地をあちこちに作っていた。アパートの裏の畑に生えた木の陰、歪んだフェンスと生い茂った草のわずかな隙間、公園の裏山の木の洞なんかに。十四箇所ほどあった基地のなかでも第五基地のスケール感は群を抜いていた。第五基地は中くらいの川の堤防沿いに生えた一本の大きな木で、長くしなやかな枝葉は地面につくほどに垂れ、幹を中心にしたドームをかたちづくっていた。その枝葉をかきわけて中に入ると太い幹から大きな枝が何本も大胆に伸び、ところどころねじれあって、怪物がぱっくり口を開けているみたいに見えた。
火塋 Les Tombeaux de feu 岩﨑元
ところで父親はぼくがやはり幼稚園にいたころから、ひとりでアカプルコだハリウッドだと海外にあそびながら、きまって旅だつまえには遺言書を更新していた。おれが死んだら会社はたたんで、ここに書かれたとおり社員の給与をはじめとする処分もすみやかに履行せよ。ゆめゆめ長じて起業しようなどとおもうな。きさまにその器量はないと父親もむすこにつとめて自誡をうながしてきたが、「さもないと兄貴につけこまれて、うちの財産は根こそぎにされるぞ」のひとことは伯父甥でも平時のなれあいはなく、むしろ元亀天正のむかしとかわらない骨肉の相剋をはりさけびそうなものだった。ただし道三霜台信長のきずなも、すこしはそこにかいまみえたかもしれない。
お玉に目盛りを付けただけ 吉野隆
僕は担任の先生に「お玉に目盛りをつけたい」と提案した。もちろん、夏休みの宿題をひとつ終わらせたかったからだ。なぜとか思いつくまでの経緯とかは説明することができない。なんとなく思いついただけの話だ。担任の先生はすぐに同意してくれて、隣のクラスの担任に相談してくれた。そしてすぐに我々の(つまり僕と先生たちの)「目盛り付きお玉」の作成が始まった。
忘れられたラプソディ(あるいは蛇) 須藤岳史
その到来の仕方は緩やかで、いつも「そろそろ来るな」という予兆がある。周囲に溢れる子供たちの声が混ざり始め、近い周波の声が溶け合い、一本の線となる。その線に囚われながらも、つい別の音色(ねいろ)の声の線を紡いでしまう。集まった線は独自の対位法により時間の流れに配置され、ポリフォニーを生む。その音響の中からあいつはやって来て、音楽の時間を止める。
流れを阻害された音楽は、時間のある一点に集約され、そこで谺する。その響きに押しつぶされるようにして空間が歪む。そして止まった時空の中で、目の前の光景が「すでに知っている」質感として再生(リプレイ)される。そこでは視覚は聴覚に追従する。
おっはみー 照子
そんなふうに、世の中には私の知らない摂理が働いていて、不思議な力に満ちていることを疑わなかった。それは呪いのようだとも思う。あの階段の五段目から飛び降りることができれば、幼稚園でずっと遊んでいられると信じていたし、特別なマントを羽織れば透明になれると信じていた。ノストラダムスの大予言を信じていた。やさしさで人は癒えると信じていた。大人になれば、自由で、気がつくと恋をしていて、家庭ができて、子供が産まれ、一切のわだかまりなく人生が回っていくと信じていた。いったいいつ魔法は解けてしまったんだろう。
リトルガールの逆襲 矢田真麻
速足で進んだ。叔父たちの家へ辿り着く途中で祖母の家を認識するはずだった。奇妙なのは、夢で見る田舎の夜に現実がそっくりなことだ。夕闇が落ちると子供はあまり外に出なかったはずだと、それから夢が素直に再現するはずはないと、二つの思い込みが作用して、夢で見たのは似ても似つかない風景だろうと勝手に判断していた。山からは水が豊かに滲み出し湖へ流れる。流れは急角度な側溝に集められ、川の上流のような激しい音を立て、昔は覆いもなく、蟹が住んでいた。
大好きなとうもろこしを食べすぎること 清水さやか
祖母もまた一本を手にし、茹でるための下処理をしていた。さやかちゃんお手伝いしてくれておばあちゃんうんと助かるんよ、ありがとねえ、と私に向かって高く細い声を出しながら、そのくせ残酷なほど力強くとうもろこしの皮をむしり取ってゆく祖母の姿には迫力があり、私もそのまねをしてなるべく暴力的に皮を剥いでいった。
こどものころは らっぱ亭
こどものころ、祖母が怖かった。
祖父が亡くなり、田舎からひきとった祖母はだんだんと口数が少なくなり、顔つきもこわばって一日中部屋で座ってじっとしているようになった。やがて昼間から寝ていることも多くなり、時折か細い声で実の娘である母を呼んだ。
「布団の裾をめくってくれへんか」
訝しみながらも、めくる母。
「何もおらへんよ」
「見えへんかったか。ちらっと赤いべべが見えたら、女の子や。おるんよ」
「きしょく悪いこと言わんとって」
「ふとんの中か、押し入れにおるんよ」
座敷わらしでも見えとるんかいな。惚けてきたらこどもに還るって言うしなあ。母は怖がりもせず、気軽な口調で言うのだった。こどものぼくに。
(遠く)見守られて 遠藤紘史
街のデザイン、BGM、住人の放つ何気ない一言。マザー2は九歳の私にとって情報が多すぎた。そして洗練されすぎていた。それらすべてが、その隅々にわたって。自分の理解の及ばないものに不足を感じることはできない。だから完璧だったし、完璧なままでいまも存在している。
あらゆる建物に入り、あらゆる人に話しかけた。語られる言葉を一粒ずつ集めていく。そうすることで、かれらの生活、その世界の仕組みがあぶり出され、よりほんものの世界のように、かれらが本当に生きているように感じられてくる。
神さまを見つけに行こう 吉野仁
イエス・キリスト、神の子、救世主。キリスト系幼稚園の卒園式における主役のなかの主役で、なぜか、その晴れ舞台の中心に自分がなろうとしていたのだ。
だが、それはあっという間にくつがえされた。幼稚園の父兄、というか母親たちによる「イエスなら、あの子だ」という声が圧倒したらしい。先生たちもそれにしたがった。けっきょく、イエス役に選ばれたのは、白尾T郎くんだった。
白尾T郎。
名前からして、すごくかっこいい。じっさい二枚目といえる顔立ちだった。眉が濃く、きりりとして賢そう。お母さんたちが噂せずにおけないハンサムな容姿だ。人を惹きつける雰囲気が確かにあった。六歳にしてどこか大人の男の魅力を備えていたのだ。
おぼえているよ 粕谷知世
おぼえているよ。
保育園の小さな机で、お昼に牛乳を飲んでいたら、ほかの子たちが机の周りをホウキで掃き始めた。埃が舞って、せわしない。そばにいた子に「どうして、お掃除しているの」と尋ねたら、「だって、もうお昼の時間は終わって、お掃除の時間だよ。ちいちゃんが食べるの遅いんだよ」と笑われた。
雷に打たれるような啓示の瞬間。
お昼の時間ってあるんだ。
みんなは、その時間に合わせて動いてるんだ。
わたしも一緒に動かないといけないんだ。
自分の周りに、自分とは別の世界が広がっているんだってこと、急に悟ったあの瞬間。
以来、わたしはご飯を食べるのが速くなった。
精華通りに 中川マルカ
異動が決まってすぐ、母は小倉の百貨店でコートを新調した。たぶん、そごうだったと思う。チェックの橙色と、無地の苔色のリバーシブルのコートだった。東京に行くんだから、と、どこか誇らしげで、それは良く似合っていた。
当時、北九州から東京まで新幹線で六時間二十分。小倉駅のホームで胴上げされた父は、灰色のそらを舞った。母と弟と、引っ越しを手伝いに来てくれた祖父と一緒に流れゆく景色を眺めていたら、別れてきたばかりのともだちが恋しくて仕方なかった。東京での最初の晩にたべたお蕎麦のつゆの色濃いことをして、父は得意げに「ははは、言うたとおりやろ、東京の出汁は、黒」と宣った。母は台所から早く使えるようにせんとね、と言い、祖父はのこしてしまったわたしの分も平らげてくれた。
転入先となる小学校のグラウンドに土はなく、プールは屋上に備わり、制服があって、先生たちはテレビと同じ標準語だった。出汁の色もことばもちがう土地で、七歳のわたしは生まれてはじめて自己紹介をした。
「はじめまして、福岡の、北九州というところから来ました」
地続きの星 佐伯紺
意味と言葉が手を繋いだのはいつだろう。
いつか母の言っていたしんどい、という響きを覚えていて、幼稚園でしんどいしんどいと連呼していたら幼稚園の先生があわててわたしの体調をうかがい、熱をはかり、熱はなかったけれどその日は外へは遊びに行けず、教室から外で遊ぶ級友たちを見ていた。わたしはしんどいと言いたかっただけで、しんどかったわけでも休みたかったわけでもなかった。
水際に立つ君へ 馳平啓樹
自分が記憶のどの部分を突こうとしているかは、はっきりしている。小学五年だったある日、急に「た」という言葉が言えなくなった事。それが「たちつてと」に広がり、「かきくけこ」にも及び、最後には、は行全体もろくに発音できなくなった頃の事。喋っている途中に出てくるのは問題ない。会話の区切りの先頭のそれらが位置するとき、「と」とか「は」とかいう最初の一文字が喉の奥から出てこなくなる。どうしてもそこに居座ろうとする。焦って引っ張り出そうとすると、「ととととびらが」とか「は、は、は、はみがきも」みたいな事になる。その瞬間、頭が真っ白になり、冷たい汗が滴り落ち、おかしな雰囲気をまき散らす羽目になる。みんなの前でものすごい恥をかいてしまう。
遺失物取扱所 しげる
デパートの壁に使われている大理石の断面にアンモナイトや三葉虫の化石が見つかることがあると、君はテレビで知った。続けて、川べりや山中に限らず、街に転がる石の中にだって化石があるかもしれない、とも。十歳の少年を興奮させるには十分な情報だ。君が当時よく遊んでいた公園は二カ所あったが、家から遠いほうの公園で石を拾うことにしたのは、おそらく、日常のなかの、しかし少しでも遠い場所に化石という物語が潜んでいることにしたかったからではないだろうか。
ただ読む、ただ遊ぶ 下楠昌哉
図書館にある限りの少年探偵団シリーズを借りて読んでいるうちに時は過ぎ、学年が進むと同時に私の識字力もあがり、物語の中身がちゃんとわかるようになってきた。しかし、読めない漢字があってもそれを無理くり突破して読み進むという癖は治らず、どうもある時期から自分で勝手に読み方を決めて読んでいたようである。この年齢になっても、たまに考えられないような漢字の読み方が記憶に定着しており、冷や汗をかくことがある。当然の報いである。そのうち、怪人二十面相が出てこない乱歩作品には、ダークな大人の世界が描かれているらしいことに気づいてきた。
窓にポポネコ王国 今井みどり
それは、猫にしては特異な風貌のぬいぐるみ一族であった。明るい茶色の短毛、身の丈、約五十センチメートル。三頭身くらいの人形型のぬいぐるみで、柔らかな手脚は自在に動かせる。キティが誕生するより、ずっと昔のこと、どこかの玩具メーカーのデザイナーがひねり出した無名ネコだ。
子ども、はてしなく 深緑野分
子どもの頃の私は、子どもであることに誇りを持っていた。大人になんて絶対になりたくなかった。大人は子どもを侮る。触ってほしくなどないのに頭を撫でてくるし、馬鹿にするし、対等に扱ったりしない。子どもが嫌がっているのに追いかけ、泣くとわかってて怖い写真を見せ、「生麦生米生卵」の練習を必死でしてると、笑うのだ。真剣な反応を滑稽と感じるなんて、侮っているからにほかならない。バスタード、大人。滅びよ、大人。当時の私が信じている大人はロアルド・ダールくらいだった。ダールは大人をやっつける正しい方法を教えてくれ、子どもを立派な人間として扱ってくれるから。
少年のころ 舞狂小鬼
ある夏の夜、父親が仕事から帰ってくるなり玄関で兄と自分を呼んだ。
「一緒についておいで。いいものを見せてあげる。」
声が少し上ずっている。靴を履いて外に出て、歩いて向かったのは家のすぐ近くに流れている小川だった。生活排水が流れる幅五十センチほどの小さなどぶ川なのだが、葦が生い茂るそこにはいつもとはまったく景色が広がっていた。冷たい光があちらこちらに明滅しながら飛び交い、葦原はまるで季節外れのクリスマスツリーのように輝いている。
「ホタルだよ。」
長くて遠い子供の時間 林由紀子
小学生の頃、小さな赤い風船を手に持って、この風船はどこまで高く上れるだろうかと、ふと考えた。家にあった一番長そうな糸巻きと風船を持って庭に出た。風船の糸の先に糸巻きの糸を結んで風船を離した。糸をしっかり握って少しずつ繰り出すと風船は真っすぐ碧空へ上っていった。弟が「持ちたい」と言ったが、渡さなかった。弟は私が何をしているのかわかっただろうか。私は一本の糸で宇宙と繋がろうとしていた。風船が見えなくなると、やがて音もなく糸が落ちてきて、私の宇宙は消えた。それほど失望しなかったと思う。あの糸をどこまでも登っていけるなどと考えたわけではない。だが、糸が手の中にあった時、その先にあるもののことを漠然と考えていた。それは一個の風船ではなかった。
プロフィール
斎藤真理子(さいとう・まりこ)
韓国語翻訳者。編み物人間。
宮内悠介(みやうち・ゆうすけ)
小説家、著作に『盤上の夜』『ヨハネスブルグの天使たち』『彼女がエスパーだったころ』『カブールの園』『あとは野となれ大和撫子』など。
北原尚彦(きたはら・なおひこ)
古本とSFとシャーロック・ホームズをメインフィールドに書いています。
桐谷麻ゆき(きりたに・まゆき)
歌人。真冬の北海道に生まれる。一六歳のころこっそりと短歌をつくりはじめる。かばん所属。
吉野隆(よしの・たかし)
一九六六年生まれ。東洋大学理工学部教授。専門は幾何学の理工学への応用。文学好き。
照子(てるこ)
一九九〇年生れ。俳人。『ヒドゥン・オーサーズ』(惑星と口笛ブックス)、『アウトロー俳句』(河出書房新社)などのアンソロジーに入集。
清水さやか(しみず・さやか)
サミュエル・ベケットについての博士論文を執筆中。
遠藤紘史(えんどう・ひろふみ)
会社員。惑星と口笛ブックスより短篇集『クォータービュー』を刊行。
粕谷知世(かすや・ちせ)
二〇〇一年『クロニカ 太陽と死者の記録』で日本ファンタジーノベル大賞受賞。そのほかの作品に、子供時代をテーマにした『ひなのころ』、『アマゾニア』『終わり続ける世界のなかで』がある。二〇二〇年二月に『小さき者たち』を刊行。
佐伯紺(さえき・こん)
一九九二年生まれ。短歌同人誌「羽根と根」「遠泳」に所属。二〇一四年に「あしたのこと」で第二五回歌壇賞受賞。二〇一八年、合同歌集『ベランダでオセロ』刊行。
しげる(しげる)
一九九〇年生まれ。「ALL REVIEWS 友の会」会員。
今井みどり(いまい・みどり)
物語のお陰で生き延びてこられた会社員。世界小説化計画に参画、綺譚作家を目指してます。
舞狂小鬼(まいくるこおに)
会社員、本好き。
夏野雨(なつの・あめ)
詩人。二〇一八年、思潮社より、詩集『明け方の狙撃手』を刊行。福岡県詩人賞受賞。
川合大祐(かわい・だいすけ)
川柳書き。
一九七四年、長野県生まれ。「川柳スパイラル」同人。著書に『川柳句集 スロー・リバー』(あざみエージェント)。
mayumiNightly(まゆみないとりー)
シューゲーズロックポップユニット ”ChelseaTerrace” とエレクトリックソロ “GrayNightly” の作詞作曲。
三月の水(さんがつのみず)
東京の西で生まれ、育ち、いまに至る。
よく行く、書店/ジュンク堂吉祥寺店、古本屋/音羽館、レコード屋/ディスクユニオン 新宿ラテン・ブラジル館、映画館/アップリンク吉祥寺。
岩﨑元(いわさき・げん)
『海豚座に捧ぐ百一発の砲声』(河出書房新社)刊行まで真木健一を名のる。なおオジキの殺気は若書きのエテュード『白い血』(河出書房新社)『微熱の夏休み』(角川書店)所収の短篇「銃声」などにも色濃くあらわれている。
須藤岳史(すどう・たけし)
ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者/文筆家。
矢田真麻(やだ・まあさ)
小説家。一九八六年生まれ。短篇集『ラヴ・ロング』ほか。
らっぱ亭(らっぱてい)
放射線科医、ラファティアン。時々、翻訳。
吉野仁(よしの・じん)
一九五八年東京生まれ。書評家。
中川マルカ(なかがわ・まるか)
一九七七年北九州市生まれ。東京都在住。マルカフェ文藝社主宰。
馳平啓樹(はせひら・ひろき)
一九七九年生まれ。作家。短編集『かがやき』(水窓出版)を発売中。
下楠昌哉(しもくす・まさや)
同志社大学文学部教授。アイルランド文学、幻想文学研究の営みを続く世代に引き継ぐことが我が責務。講道館柔道五段。
深緑野分(ふかみどり・のわき)
一九八三年十月六日生まれ。
自分の誕生日が好きすぎて数字の中で「6」を異様に愛しています。
割りやすいし。
林由紀子(はやし・ゆきこ)
一九五八年東京生まれ 銅版画家。