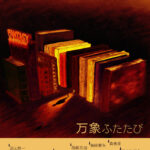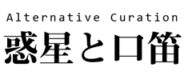佐川恭一は小説の作法や儀礼に頓着しない。なのでひじょうに行儀の悪い作家に見える。
佐川恭一は通俗的で猥雑である。だからあるいは読んでいて眉をひそめる読者もいるかもしれない。
しかし考えてみてほしい。眉をひそめたということは観念に過ぎない小説というものが、人の肉体に変化を生じさせたということなのだ。肉体に変化を生じさせる小説を人は決して軽んじてはならない。
これはこれまでになかった超青春小説集である。ピーテル・ブリューゲルやボスのごとく現代の若者を描くこの作家を試しに読んで欲しい。俗からきざす聖性、不思議な抒情を。行儀の悪い作家がいま文学に新しいテイストを携えてやってきた。
収録作は「光のそと」「ポートレート・オブ・ア・ジャパニーズ・ファミリー」「冷たい丘」「講師と女生徒」「透明な檻」「公園」「饗宴」の7作品、400字詰め原稿用紙換算約200枚。表紙イラストはすわみ。
価格600円。
作品抜粋
透明な檻
臙脂色の体操服を着た五十四名の生徒たちは次々に呼び出され体育教師の放るバスケットボールを受け取り二度のドリブルをしてレイアップシュートを放ち約七割がゴールを決めた。残りの三割の生徒は二巡目に入り、その繰り返しでゴールを決められない者が取り残されていき、最後に一人、亀井という生徒だけが全く課題をクリアできる様子もないまま、五十三名の心ない観客に包囲され立ち尽くしていた。「落ち着いて、落ち着いてやればできるぞ」体育教師が励ましの言葉をかける。体育教師はどんな分野においても、努力さえすれば誰でも一定以上の成果 を得られると信じている熱心な共産主義者だった。心ない観客たちは亀井をせせら笑ったりあくびをしたり互いに英単語の問題を出し合ったりした。彼らはある田舎の進学校の二年生だった。
亀井が一度もシュートを決めないまま体育の時間は終わりを告げ、体育教師は放課後に体育館にやってくるよう亀井に命じた。「すみませんが、今日は塾があるのです」亀井がそう言うと心ない観客たちは「今日は塾があるのです」と亀井の特徴のあるアクセントを真似してはやし立てた。体育教師は生徒たちを一喝して沈静化させてから、亀井の頬をひっぱたいた。学校は勉強のためだけにあるのではない、立派な人間になるために様ざまな経験を積む場所なんだ、お前がレイアップを決められないまま塾に行くことは許さないぞ。
心ない観客たちは無関心な五十三名の生徒へと姿を戻し七限目の「家庭科」が終わるのを膨大な量 の宿題が出されている数学の問題集をやりながら待ち続けた。クラスで一番数学のできる亀井だけはすでに数学の宿題を片付けていたため苦手な古文の文法を暗記していた。授業が終わる五分ほど前、家庭科の教師が机を両の手のひらで叩き付けながらほとんど叫んだ。「今は数学の時間ではありません!」生徒たちのほとんどは手の動きを少しずつ緩やかにして止めた。お裁縫もお料理も生活に必要な、とても大事なことなんです、今のあなたたちにはわからないかもしれないけれど、あの時に聞いたのはこういうことだったのかと思う日がきっとくるはずよ。涙声になっている家庭科の教師の話に耳を傾ける者は一人もおらず皆手を動かすのはまずいと思っただけで頭の中で数式をこねくりまわし亀井は古文の助動詞の意味を反芻していた。しかし家庭科の教師は大人しくなった生徒たちを見て少なからず満足した様子で教室を出た。帰りのホームルームが終わるとある者は図書室へ向かいある者は塾へ走り出した。
亀井は机から動かず少しだけ長く目をつむった後で、制服のまま学校を出た。
ポートレート・オブ・ア・ジャパニーズ・ファミリー
大学時代、ナカムラには椎名林檎ばかり歌っているミズノという彼女がいたが、それは彼女が椎名林檎を大好きだったからではなく、ナカムラが椎名林檎を大好きだったからで、そのことにナカムラはぜんぜん気付かないまま、大学卒業と同時にラインで別 れた。「ほんまめっちゃ腹立つ」ミズノはひどくお怒りである。
「まじでラインで別れてくるとか。ありえん!」
ナカムラがラインで別れをせまってきたのは卒業式の日のことだった。卒業式に呼んだ、娘の成長に感動でふるえている母の横。ミズノは無防備な心にぴかぴか輝く手榴弾を突然投げ込まれ、無惨にも爆殺された。
「ほんま、あんたも立派になったもんやな。お母さんめっちゃうれしいわ」
「……」
「あんたちっさいときほんまに大変でな、お父さんもぜんぜん面倒みいひんし。あんまり泣くさかいに、三日にいっぺんぐらいやったかなあ、お母さんが自転車の後ろに乗せて、夜中にあれしたったん覚えてる?」
「……」
「ん、どしたん?」
「いや……」
「なんやの? 誰から?」
「いや、なんでもない」
その後一日じゅう、親子の会話は弾まず、卒業式後の友人らとの飲み会も、ぜんぜん楽しめなかった。人生においてかなり重要なはずのその一日を、ミズノはナカムラにつぶされたのである。
A社に就職したナカムラはやがて大阪に配属され、B社に就職したミズノはやがて東京に配属された。ミズノが部屋に揃えていた椎名林檎のCD群は彼氏と趣味が合うふりをするためのアイテムだったが、就職の際、いちおう東京にもってきて、しかしみているといらいらするので、ばき、ばき、と一枚ずつ割って、地域の指定にしたがい、燃えないごみの日に捨てたのだった。
「CDは燃えずとも」とミズノはいう。
「うちの憎しみは燃えさかっておる!」
ミズノは同期のサカベを大衆居酒屋に呼び出し、右記のやり場のない怒りについて相談するのだった。「やり場がないっていうか」とサカベは冷静である。
「別に、直接いえばいいじゃない。ラインで別れるとかありえないって、元カレに」
「いや、でもいまさらそんなんいえへんやん。だいぶ時間たってるし」
「多少遅れてでも、いいたいことはいったほうがいいんじゃない? 現にミズノさんはそれで苦しんでるわけだし。そうだ、それこそラインでいえばいいじゃん」
「天才あらわる」
ミズノは早速、激安の焼き鳥をほおばりながら爆速でラインを打つ。サカベもミズノもハイボールをたらふく飲んでいて頭が普段の半分もまわっていない状態だったが、本人たちはそれに気付いていない。むしろいつもより冴えているつもりである。
ひさしぶり。てっちゃん、元気してる? 仕事はうまくいってる? うちは大丈夫やで。あのさあ、たまに思うんやけど、うちら最後なんでラインで別 れてしもたんやろ。なんでちゃんと会って、話し合わへんかったんやろ。なんか、別 にヨリ戻したいとかじゃなくて、もう一回だけ、会ったりできひんかな?
送信されたその文面をみたサカベはハイボールをわずかに噴射して「これ、ぜんぜん怒れてないけど大丈夫?」といった。
「いや、ぱっとみは怒ってへんけど、ねちねち攻める作戦やん。ボディブローのようにきいてくるやつよ」
「うーん、いわれてみればそうかも」
「せやろ? 我ながらけっこういい線いってる思うねん」
「だね! まあ、ボディブローもらったことないけど」
「いやーほんますっきりしたわ! ありがとう!」
「ううん、私みたいなのでよかったら、いつでも相談して!」
これでふたりの友情はふかまったかにみえたが、ラインの返事がいつまでたっても返ってこなかったため、なんとなく会うのが気まずくなり、結局、すれちがった際に軽く挨拶するのみの仲に生涯とどまった。ミズノの送ったラインには死ぬ まで既読がつかなかった。なぜならナカムラはミズノをブロックしていたからである。
「おれは過ぎたことはふりかえらん。意味ないから」
ナカムラはそういう考え方をする人間だった。これにはいい面もあれば、だめな面 もある、と母ナカムラは思っていた。
テツヤは嫌いになった相手との関係を簡単に切りよる。それで意地みたいに二度と修復せえへんから、長く続いた友達とか彼女がおらんし、どんどん新しい友達つくって彼女つくって、みたいになるから、たぶん結婚とかもできひん。人として大丈夫なんやろか。
母ナカムラはおおよそそのように息子を案じているが、当のナカムラはぜんぜん自分の生き方に迷いがない。明るいタイプのナカムラは職場でもうまくやって、同期とも先輩とも仕事をするには十分なほど仲良くなり、係長には特に気に入られ、係や課の飲み会の幹事は大体任されるようになった。ナカムラはそういうことを苦にしない。頼まれてもいないのに簡易ビンゴゲーム機などを買って、ノリノリで司会までつとめる始末である。
一方、同じ課の同じ係に配属されていたナカムラの同期ヤノは、ナカムラに比べて評価が低かった。
暗いし、キモいし、仕事遅い。
それがヤノの大方の評判であった。この古い体質のA社では総合職が男性、一般職が女性という風にほとんど綺麗に区分けされていて、特に一般職の女性陣は、ヤノをごみのように扱った。ヤノは世間的には一流とされる大学を出ていたが、部活やサークルに所属しておらず、一方のナカムラは、ヤノよりも低いランクの大学出身ではあったものの、体育会系のサッカー部に所属していた。それが大きな差となってあらわれている、というのが一般職の中でオツボネと呼ばれているテラオリカの意見である。テラオリカは長年同じ課にいるため、三年ほどでころころ変わっていく総合職の課長や課長代理などよりも仕事にくわしい。また結婚を是としないキャリア・ウーマンタイプの極北であり、さっさと寿退社をキメていく一般職女子たちのこともごみだと考えている。
「中途半端な気持ちで仕事しないで。もしも腰掛けのつもりだったら、いますぐ辞めてください」
テラオリカは毎年入ってくる一般職女性に対して、そのようにいう。発破をかける。したがって、一般 職女性が結婚を発表する場ではつねに緊張が走る。みな、笑顔で拍手を送りながら、テラオリカの顔色をうかがうのである。大抵、氷のように冷たく硬い表情をしている。どいつもこいつも、ごみばかりだわ。いまにもそういい出しそうな表情なのである。
プロフィール
佐川恭一(さがわ・きょういち)
滋賀県生まれ。京都大学文学部卒。著書に『サークルクラッシャー麻紀』、『童Q正伝』、『終わりなき不在』、『シュトラーパゼムの穏やかな午後』、『無能男』など。2019年現在、小説すばる(集英社)にてコラム『愛すべきアホどもの肖像』を連載中。