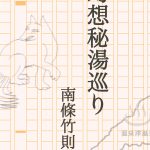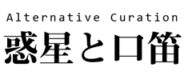日本ファンタジーノベル大賞の優秀賞と大賞受賞者による書き下ろし巨大アンソロジー
常識を超えたギガンティックなファンタジーのアンソロジー。原稿用紙換算で千枚超、文字数にして四十万字弱、一般的な単行本で三冊以上の分量です。そしてそれがすべて書き下ろしです。アンソロジーですが、三百余枚の長篇 「サナギ世界」関俊介が丸ごと収録されています。もちろん前例のないことです。
参加者は十八名で作風は日本ファンタジーノベル大賞の傾向そのままに多岐にわたります。想像力への旅をお楽しみください。
小田雅久仁「旅路」
主人公はホテルの一室で目をさます。なぜそんなところにいるのか自分にはまったくわからない。そして隣には裸の女が寝ている。左手首を見るとそこには腕時計にも似た奇妙な黒い機械が肉に喰いこまんばかりに装着されている——異才にして鬼才のめくるめく恐怖と幻想の異世界周遊をどうぞ。
粕谷知世「いき・かえり」
子供時代は神話として現在も残る。神話的な通学。叙事詩的想像力の作家からうまれた詩的短篇。
西崎憲「影機」
蕃東国シリーズ未来篇。父親という概念にとりつかれた影の機械。
日野俊太郎「鬼街」
戦のある地に忽然と出現する遊郭。凄艶な鬼の遊女たちと醜い名無しの男。妄執の果ての昏い物語。
南條竹則「温泉叙景」
ノンシャランな幻想譚の書き手にして怪奇小説の名訳者はエッセイの名手でもある。温泉と猫。
冴崎伸「空想の現実~ミャンマーの沼/ぼくと博士の楽しい日常〔裏の目薬〕の巻」
冴崎伸はプロ格闘家から起業家に転じ現在は複数の会社の役員であるという。物語のなかにしかいないような稀有な実業家ファンタスト。アジア小景とユーモア児童文学の二篇。
北野勇作「『クラゲ怪獣クゲラ対未亡人セクシーくノ一 昼下がりの密室』未使用テイク」集
進みつづけるSF作家。いやSFではなく、もうジャンルは「北野勇作」かもしれない。不穏な世界の不可知のくノ一。
石野晶「死人花」
独自のリリシズムと空想、幻想の作家。死者の記憶をたくわえる死人花(しびとばな)、朝霧のなかに玻璃の儚さで咲くその花が伝える真実とはいかなるものだったのか。
大塚已愛「せみごゑ」
記憶をなくしたまま島に流れ着いた男。そして目の前に現れた蝶を嚥下する少女、不思議な男、島の生活。鮮やかで切ない幻想譚。
久保寺健彦「立ち入り禁止」
少年少女のなかにある暗渠に似たなにかを描くとき久保寺健彦は冴えに冴える。そして暗渠はおそらく消失することはない。あなたやわたしの暗渠。
森青花「ちゃとらのチャトラン」
極限にまでテンポを落とした脱力的レトリック。しかし深い希求。猫への愛。存在への愛
斉藤直子「大地は沸かした牛乳に」
文体家(スタイリスト)の多い日本ファンタジーノベルの作家のなかでも特筆すべきスタイリスト斉藤直子。「ゴルコンダ」にはじまる「僕と先輩」シリーズ最新作。オフビートかつ軽快なユーモア。
三國青葉「ばっくれ大悟婆難剣 冬虹」
大らかでのんびり屋だがじつは腕もたつ大悟と将軍吉宗の母由利のライトハーティドなシリーズ三作目。今回は「フグ」をめぐる騒動。
柿村将彦「反省文」
異才の数は世に少なくないが柿村将彦は新時代の異才である。学校に遅刻して反省文を書かされた主人公が語る遅刻の理由。一風変わった想像力と感情の機微を書きわける修辞力の貴重な合体。『万象ふたたび』 の「こいだま」も刮目すべき傑作。
藤田雅矢「ブランコ」
エヴァーグリーンなSF作家。本作は町の博物誌+世界の危機という魅力的な結合体。SFはけっして終わらない。
堀川アサコ「3つの生け簀」
堀川アサコは世界や人間の湿った部分を描くことに巧みである。読者の多い作家になったのはそのことが理由のひとつだろう。本作は日常を侵食する伝奇を描いたものである。
勝山海百合「紫には灰を」
切れ味のある修辞で人と人とのつながりを描く勝山海百合は、コレクションをするように小宇宙を造りつづける。今作では「染色」が未来と古代をつなぐ糸となり、それは同時に人と人も結ぶ。美しい未来譚。
関俊介「サナギ世界」
遠未来。ヒトがすでにいない地球で生きるヒト派生種のバッタたち。捕食される種に生まれた者たちの冒険、苦闘そして希望。関俊介も本作の登場人物たちのように知恵と勇気と根気でオリジナルな視点と発想に満ちたファンタジーを作りあげた。本作は今後日本のファンタジー史における異貌の傑作として言及されるだろう。
表紙は井村恭一。価格1000円。公式X(ツィッター)アカウントは@10000zo。
収録作抜粋
「旅路」小田雅久仁
『次は罪人番号九一七号!』
骨まで透けるような凄まじい光に、弘幸は目が眩んだ。怖ごわ目を開けると、真っ白な光芒の中に一人座っていた。ほかの囚われ人たちはみな暗がりに沈み、こちらを見たり目を伏せたりしている。俺か? 次は俺なのか? 弘幸は肩越しに振りかえった。黒子がすでに注射器を構えてこちらを見おろしていた。そしてなんの前口上も予備動作もなく注射器を近づけてくる。
右の首筋に針が刺された。その瞬間の痛みは微々たるものだった。が、数秒後、刺されたところで熱のような痺れのような塊が生まれ、瞬く間に血肉を沸騰させながら全身にひろがってゆく。体が勝手にびくりびくりと震え、口がひらいて顎がねじれ、「ぐえるごああああっ」という自分のものとも思えない呻きが漏れだす。全身の毛穴という毛穴が内側から押しひろげられてゆくような感覚が起こってきた。勝手にのけぞろうとする首をどうにか抑えこみ、おのれの体を視界に入れる。ぷつぷつと黒い泡のようなものが太股に夥しく浮きあがりだしたかと思うと、その泡が大きくなりながら蠢きながらにゅるると盛りあがり、ぽろりと両腿のあいだに転げ落ちた。
虫だ! 四、五センチはあろうかという黒い幼虫のようなものが、全身の毛穴を押しひらいて俺の体から這い出てくる! 胸や腹からも次々に幼虫が出てき、幾対もの脚をぞわぞわと動かして肌の上を這いまわったり、脚のあいだに落ちて組んずほぐれつ転げまわったり、草食獣の糞のようにころころと床に散らばったりしている。数十匹、いや、もう数百匹はいるだろう。どの虫もむっちりと肥え太り、鈍く黒光りする蛇腹状の体を波打たせている。全身の皮膚が泡立つように痺れ、これぞ痛みと言える明確な感覚はないが、こいつらは俺の体を内部から喰い荒し、ここまで成長したのだろうか。そうとしか考えられない。実際、しだいに肉体が黒ずみながら枯れはてるようにしぼんでゆくのだ。囚われ人たちのあげる悲鳴や観客のどよめきが聞こえてきたが、耳の中からも幼虫が這い出てくるらしく、分厚い瓶にでも押しこめられたようにたちまちすべてが遠ざかる。ぷちりと音がして右手の視界が歪んだかと思うと、次に左も歪み、すぐに一切が暗転し、何も見えなくなった。どうやら眼窩から生まれ出た虫が眼球を破壊したようだ。もし眼球が健在だったとしても、弘幸はもはやろくに何も見えていなかっただろう。きちきちと奇妙な音を立てて蠢く幼虫に顔面を、いや、全身を黒ぐろとおおいつくされていたからだ。
「いき・かえり」粕谷知世
山といっても高くはない。古墳群ではないかと想像を誘う、お椀形の小さな山が点在している。その間を小川は南北に流れ、その小川に沿って敷かれた国道が村を二つに分けていた。陶土を運ぶダンプカーが常に行き来する、交通量の多い道だ。
秋野の家は、その国道を見下ろす山のふところにあった。彼女の祖父母が建てた木造二階建ての母屋は、まるで王が臣下を従えるように車庫や藁小屋、農機具小屋に囲まれていた。中庭には、父が据えつけた赤いブランコが置かれている。
その家で、秋野は生まれて育った。
永遠に近い時間だった。
保育園へ行き、帰ってきたら隠居の祖母と一緒に再放送の時代劇をみる日々は、大河のようにゆったりと過ぎていった。
いよいよ小学校へ上がるとなった時、父に訊かれた。
「学校へ行くようになったら、七時には家を出んならん。そのためには六時起きになるが、秋野はちゃんと起きられるか」
「起きられるよ」
秋野は即答した。六歳の秋野に不可能など存在しない。それが何を意味しているのか、それによってどんな思いをすることになるのか分かっていないのだから、どんなことでも、できるに決まっているのである。
「影機」西崎憲
ロボットに会ったのは数ヶ月前のことだ。偶然の邂逅と言えるだろう。けれど「会った」というのはだいぶ迂遠な表現である。すこし詳しく記すならば、わたしはかれに救われたということになる。ロボットはわたしを助けた。死のうと思って川に飛びこんだところをロボットが救ってくれたのだ。ロボットはわたしを川から引き揚げ、水を吐かせ、人工呼吸をほどこした。おかげでわたしは息を吹きかえした。しかしそのことの是非をいうのは難しい。わたしは死んだほうがよかったのかもしれないといまでも思っているのだから。
わたしはミダス王に似ている。ミダス王が触れるものをことごとく黄金に変えたように、わたしは触れるもの扱うものをことごとく負債にあるいは塵芥のようなものに変える。それはわたしの運命だったし、自分ではどうしようもないことなのではないかと思う。
親から引き継いだ相当な資産を愚昧さゆえに雲散させ、多額の借金をこしらえ、精も根も尽き果てたわたしは死ぬしかないと思った。なにより生きていることが面倒になった。だから橋から深い川に飛びこんだ。
わたしの事情はそういうものだ。そしてロボットのほうにも事情があった。
そのロボット、人間型の人工知性は黄孔という名前だった。
黄孔は大きな邸にひとりで住んでいた。わたしとちがって黄孔は成功者だった。ロボットの成功者のなかでも成功の度合いは飛びぬけていて、人間と同じ権利を持っていた。通称Hカードを持ったこの国で十七体のうちのひとりだった。
そして電力の供給システムの開発で莫大な資産を得た実業家である黄孔は同時に詩人でもあった。
「鬼街」日野俊太郎
名無しは比丘尼の言に従い、彼女の身の回りの世話をする下男となった。とは言っても、負った傷は深く、初めの一月は伏せたきりでほぼ身動きを取ることも出来なかった。時折イブキがやってきては体を拭いたり、飯を食わせたりしてくれるのが彼の生きるよすがだった。
五日数えるたびに、家因が仕返しに来るのではないかと心が休まらない夜が続いたが、あれ以来家因の相手をしたという遊鬼は現れなかった。
やがて傷も癒え、名無しはこの街に暮らす遊鬼たちと「人」らしい関わりを持つようになっていった。人並みの暮らしをしたことのない彼にとって、鬼の女たちとの生活は心を満たしてくれるものであった。
「オババ、大門を開けてくる」
比丘尼が自身のことをそう呼ぶのに倣って、名無しもいつしか彼女のことを御婆と呼ぶようになっていた。
鬼の女たちは皆、比丘尼のことを慕っている。日がな一日、彼女の座敷には誰かが入れ替わり立ち替わり訪れており、それを見て名無しはまるでトメ婆(ばば)みたいだと思った。
トメ婆は川中村でただ一人の産婆で、村中の者が一目置いていた。身寄りのなくなった名無しを引き取り育ててくれた人である。少なくともトメ婆が死ぬまでは、名無しは人の端くれとして生きてこられたのだ。
名無しは大門の前に立つと、通りの軒先で客を待つ遊鬼たちに大きな声を張り上げた。
「これより里を開きます。皆々今宵も、たんとお上がり」
この文句は御婆の受け売りだ。大門の開け閉めは里の主人の仕事である。彼女が開門する前にこう声を張ると、鬼たちが「真っ平ごめんさ」と陽気に返すのが習いとなっていた。
「温泉叙景」南條竹則
微温湯温泉に行き始めた当時、宿では二匹の猫を飼っていた。
一匹は黒い虎猫で、小虎という。もう一匹はゴマサクといい、その名に似合わず雌の茶色い虎猫だ。この二匹はかなり長生きして、死ぬ時は相次いで死んだ。その後、しばらく猫がいなかったが、ある年に行くと、金目銀目の白い雌猫がいた。
宿の人は「お嬢」と名づけていた。
お嬢は少し体形が普通の猫よりも長細い気がする。それに、夜中にかすれた妙な声で鳴く。どうも外国産のようだ。
じつは、吾妻山の微温湯よりずっと下の方に「ワンニャンランド」という施設があって、外国の犬や猫をたくさん飼っていた。そこが最近閉園し、どさくさに逃げ出して来たらしい。
お嬢はやがて子猫を四匹生んだ。
黒い虎猫の二代目小虎と茶色い虎猫の二代目ゴマサク。それに白猫のお千代とお小夜。
二代目の小虎は雌だ。先代は人なつこく、わたしの部屋へ入って来てプルプルと小便をしたことなどもあるが、二代目は少しもそばへ寄って来ない。
「小虎は雪乃の猫なんですよ」
と女将(おかみ)さんが言った。
わたしは「はあ」と聞き流したが、しばらくして女将さんの言った意味がわかった。
雪乃ちゃんというのは、この家の小さい女の子だ。おかっぱ頭に林檎のような赤い頰をして、廊下を元気良く駆けまわっている。小虎は始終この子にくっついて歩くのだった。
「空想の現実 ミャンマーの沼/ぼくと博士の楽しい日常〔裏の目薬〕の巻」冴崎伸
「仲本社長、ミャンマーは暑いでしょう」エイさんが太い眉毛をこすりながら言った。
「暑いね。日本よりもとても」
ちょっといい加減なものだと思って、わたしは苦笑した。上野の中華料理屋ではじめて会ったとき、エイさんが『ミャンマーより日本のほうが暑いです』と言っていたことを記憶していたからだった。
面白いことに、これはベトナムやインドネシア、カンボジアなど、東南アジアであればどこもおなじようだ。かれらは日本にいるあいだは「日本の夏のほうが暑い」と言う。しかし、かれらの国にくると「どうです、うちのほうが暑いでしょう」と笑いながら言う。
東南アジア共通の、日本人向けジョークなのかもしれない。あるいは地球温暖化で生まれたジョークか。
「エイさんの会社は、空港から遠いですか」
ターンテーブルを次々に流れてくる色とりどりのスーツケースを見ながらたずねた。
「車をよんでます。一時間くらいです」
「エイさん、女性たちが目の下につけているのは何。化粧ですか」
その場には五〇人ほどの女性がいたが、ミャンマー人とおぼしき女性たちはみな、両目の下に白っぽく、太い線をひいていた。
「ああ、タナカです」
「タナカ? 日本の名前みたいだ」
「タナカの木からつくったのを塗ります。ええと、おしゃれね。あとすこしだけは、悪いことがないように」
エイさんが手真似をまぜて、説明してくれた。
「魔よけということかな」
「そうです、仲本社長」
「もう仲本でいいよ、エイさん」
「仲本さん」エイさんがにこりとした。
エイさんはとてもよく笑うとこのとき思ったが、この国の人は、本当によく笑うと後で知った。
「『クラゲ怪獣クゲラ対未亡人セクシーくノ一 昼下がりの密室』未使用テイク集」北野勇作
ああそれも聞こうと思ってたんだよ。その、変装って、どういうことだ? 奥さんはそんなにすぐ変装したりするのか?
するなんてもんじゃないです。変装名人ですから。
変装名人ったって、そんなのホクロだのヒゲだのズラだのをつけたり外したりするくらいのもんだろ。
いやいや、そんなレベルじゃないです。太ったり瘦せたり高くなったり低くなったり老人になったり子供になったり指紋を変えたり声紋を変えたりもしますね。
おいおい、その奥さん、いったい何者なんだ。それじゃまるで、スパイか忍者じゃないか。
ええ、そうです。
なにがそうなんだよ。
忍者っていうか、ずばり、くノ一なんです。
なんだって?
知りません? 女の忍者のことをくノ一って言うんですよ。
それは知ってるよ。
知ってるんじゃないですか。なんでも結婚前にどっかの会社で、くノ一をやってたらしいです。いわゆる企業くノ一ってやつですかね。
企業くノ一?
ええ、敵対する会社の密書とかを奪うんです。
それって、産業スパイってこと?
いえ、断じて、くノ一。
まあどっちでもいいけど。
なんでも、もともとは、うちの会社の機密を探ろうとして彼に近づいたんですけどね――。
あの、その話って、長くなる?
そりゃまあロマンスあり裏切りありですから、けっこう長くなると思いますが。
それじゃ、続きは作業しながら聞こう。早くやらないと腐り始めちゃうからな。
とにかくそんなわけで、四人の変死体には、あの逃げ出した実験体と同じものが注入される。そしてそれは、注入されるとさっそく活性化し、自らの周囲の環境の最適化に取りかかったのである。
「死人花」石野晶
高鳴る心臓の音を感じながらしゃがみこむと、敷石の前に、私はそれを見つけた。
一輪の、花だ。
見かけは花だとは思えない。朝日を浴びて銀色に透き通るそれは、ガラス細工にしか見えないのだ。
しかし触れてみれば銀の花びらは柔らかく、私の指が透けて見える。形はサフランの花に似ている。銀の花びらに包まれた中には、黄色のしべが一本、すっと伸びていた。
緑色の茎を親指と人差し指で抑え、中指で力を加えると他愛なくポキリと折れた。
花びらの内側を、スウッと溜まった露がすべり落ちていく。
差し始めた朝日に花をかざすと銀色に透き通り、花びらの中の筋が浮き上がる。それは何かの紋様のように、銀の器を彩っていた。朝露が甘露のごとく光り輝く。
村人達は、誰もこの花の存在を知らない。
花を手折るのは、代々の墓守の特権とされてきた。
墓守は誰よりも早起きで、朝一番に墓地を訪れる。そして花を見つけたなら、摘んでしまう。誰にも見られないうちに。
代々の墓守はこの花を、死人花(しびとばな)と呼ぶ。
「せみごゑ」大塚已愛
寄せては返す波の音は、何処かで自分を呼ぶようでもあり、また、責めているようでもある。何のことはない、自分は眠るのが怖いのだ、とぼんやり思う。眠れば、また夢を見るのだろう。
秋水は、布団の上から立ち上がると、ふらっと社の外に出た。月明かりのおかげで、地面に影が映るほどに外は明るい。
海へ行こうと思ったのは、多分、何かの偶然だった。
長い石段を降り、土の道を踏みしめて例の浜辺へと歩く。濤声(とうせい)が近づくにつれ、月明かりに照らされて、浜辺に二つの影があるのが見えた。
砂浜に立つ青年と、膝の辺りまで海に浸かったあの少女だ。夜光虫でも居るのだろうか、波の一部が打ち寄せる度、青く輝くのが見て取れる。一方の、砂浜に立つ青年の足下には、三振の刀が突き立っているのが見えた。
月の光を反射させ、刀身は尚青く輝いているようだ。青というのはもの悲しいと、ぼんやり思う。
秋水に気がついたのは少女の方が先だった。秋水を認めると、少女が微かに眼を細める。彼女の視線に気付き、青年が振り向いた。
「なんだ、お前も海に来たのか。ちと早いが、まぁ、手間が省けて好(よ)かったな」
「……手間?」
「お前の番が来た時に、説明をする手間が省けたということだ」
そう言うと、青年は、少女の足下に打ち寄せる波を指差す。夜光虫のように発光するその水は、しかし、夜光虫のような蛍光ではなく、もっと違う何かの燐光のようだった。
からからと笑う青年に、少女が茫とした眼を向ける。その眼を受けて、真面目くさって青年が言った。
「どうやらすべてが整ったようだ。では、はじめるとするか」
青年は、少女に中茎(なかご)が剝き出しの三振の刀をそっと手渡す。少女は刀を、水の中にそっと沈めた。切っ先が海へ触れた途端、波紋のように青い光が外へと広がる。それに併せて、青年が朗々とした声で祝詞を読み上げた。
「立ち入り禁止」久保寺健彦
久美子は、消防通りに面した美容院の子だった。店はクリーニング工場の横にある雑居ビルと、ラーメン屋にはさまれた建物の一階。入り口の脇にとりつけられた、「美容/着つけ」と交互に文字があらわれる回転灯といい、あせた飴色のガラス扉といい、いかにも場末の雰囲気だった。
店の二階が四戸のアパートで、久美子と母親はそこに住んでいた。母親の仕事柄、久美子の身なりは凝っていた。パーマをかけていたこともあるし、ピアスをしていたこともある。大人っぽくてものおじしない久美子には、だれも逆えなかった。しょっちゅうその界隈でケードロをしたのも、そもそもケードロをするようになったのも、久美子が言い出したことかもしれない。
ぼくは逃走範囲の境界内を、丹念に捜索しなおした。何度かほかの刑事の姿を見かけ、そのたびにドキッとした。むこうも気まずそうで、お互いに牽制しあうムードがあった。児童遊園に寄ると、囚人たちの遊びは棒倒しに変わっていた。さっきとは別の一人が話しかけてきた。
「まだ?」
「うん」
「ふーん」
囚人たちが顔を見あわせ、せんべいをかじった。牢屋を抜け出して買いに行ったわけだが、ケードロも終盤にさしかかると、その辺は毎回いい加減だった。
クリーニング工場からシューッシューッと蒸気の音があがり、消防通りからはひっきりなしに、車の走行音が聞こえてくる。団地のベランダには、布団が何枚も干されていた。さっきまでそれを叩いていた主婦も引っこみ、あたりにはぼくと囚人以外、だれもいなかった。
ふと、久美子はアパートにいるんじゃないか、と思った。ルール違反だがやりかねないし、そう考えればこれまでに、一度も見つからなかったことの説明がつく。
あたりをうかがい、ほかの刑事がいないのを確かめてから、足早に消防通りへむかった。肩越しに振り返ると、児童遊園は死角になり、囚人たちは見えなかった。
すばやく角を曲がる。ガードレールのむこうの排気音が、急に大きくなる。雑居ビルと美容院のあいだの鉄階段を、足音を忍ばせて二階にあがった。合板のドアが四つ並んでいる。久美子の苗字の表札は、手前から三番目だ。廊下を歩き出し、なにげなく手すりのむこうを見たとき、予想だにしなかったものが目に飛びこんできた。ヒメジョオンの花が咲き乱れる空き地の奥に、久美子が横たわっていた。
その日の久美子は、レモンイエローのTシャツに、赤とグレーのタータンチェックのスカートを身につけていた。謎が解けた喜びも忘れて、色とりどりの花に埋もれている姿に見とれた。が、すぐにうろたえた。久美子がどうやってそこまで行ったのか、わからなかったからだ。
「ちゃとらのチャトラン」森青花
チャトランの住む「ねこのまち」は、今日ものどかです。
ほら、そこに、チャトランがぽーっとしています。
「大地は沸かした牛乳に」斉藤直子
大地は沸かした牛乳に張った膜のようなものであるという。
レンチンしすぎた麦芽乳飲料を僕はデスクに運びつつ、そんなことをふと思う。
ユーラシアやら北米やらのプレートは、膜がひととき平らになった面、南海トラフや糸静は、ほんのひと寄りしたシワだ。伸び縮みだけで大惨事、破れたならば僕らは沸き立つアセノスフェアに、
「ずぶずぶ沈んでエンドです」
――これの練習しときゃいいのかよ
PCのモニタに映る先輩が、親指を立て「ででんでんででん」と口ずさむ。
「webカメラに指紋を晒すの禁止です」
――社員しか見えねえやつだろ、この画面
「社内ツールも流出リスクは絶えずありますから」
しかも僕も先輩も、いまは自宅でリモート接続だ。ご家庭のプロテクトなど歴戦のプロ侵入者には牛乳の膜にも及ばぬフニャ障壁、
「在宅ワークは常在戦場なんですよ」
――家の外には七人の敵ってな時代が懐かしいわ
先輩はぼやいてギュっと親指を登下校時に霊柩車を見た小学生のごとくプロテクト、
――もとの世界に早く戻らねえもんかな
「そういえば僕の奈良のおばあちゃんも」
維新のときもみな早う徳川の世に戻りゃええのにちゅうとったわ、
「って」
――戻れなかったやつじゃねえか!
縁起でもねえ、と先輩の声がPCのスピーカーをハウらせた。
じっさい僕らの世はまさに、縁起でもないことになっている。
粘膜に細胞膜に核膜に、ヒトの内にも幾重にも張り巡らされた膜がある。それらをやすやすハックする新型ウイルス爆誕で、あれよあれよとパンデミックなのだった。馴染みの学級閉鎖から、学校閉鎖・都市封鎖・国境封鎖とマクロに幕が引かれゆき、庶民はミクロに世帯封鎖とあいなった。どこへも行かず誰にも会わず、ひたすらに家にこもって病魔退散を待っている。
「国家総動員物忌みやな、って奈良のおばあちゃんが」
――ばあちゃん時代感バグってね?
「僕のこともシュレディンガーの孫や、って」
――もはやナニ感がバグってんのかすらわからんわ
「ずっと会えない僕が部屋でひとり大丈夫なのかダメなのテテケテッテケテッテー」
――大丈夫かよー!
「アラートです」
「ばっくれ大悟婆難剣 冬虹」三國青葉
急にごうっという音とともに強い風が吹き、雪を巻き上げた。いぶかしみながらも、大悟はせっせと足を運んだ。
近づいてみると、やはり少年であった。顔は笠で隠れていてわからぬが、背格好から見て十一、二というところであろうか。
子どもがこんなところで誰を待っているのか。まさか親ではあるまい。
すれ違うとき、少年が顔を上げて、大悟をちらりと見たので目が合った。前髪立ちで目は切れ長。利発そうな顔立ちをしている。
少年は大悟からすぐに視線をはずし、再び橋の上を見つめた。橋を渡りきった大悟は、少年が思い詰めた表情をしていたのが気にかかり、足を止めて振り返った。
少年の華奢な肩には、雪が降り積もっている。どのくらいの間ここにいるのかは知らぬが、身体はおそらく冷え切っているのではなかろうか。
このままでは、きっと風邪をひいてしまう。声をかけ、熱い蕎麦でも食べさせてやろう。
そのとき、少年に緊張が走った。つられて大悟が向こう岸を見ると、傘をさした男がひとり、橋を渡ろうとしている。
背はそれほど高くないが、かなり肥えていた。突き出た腹が狸を思い起こさせる。
少年の肩が上下し、息が荒くなっている。大悟は愕然とした。少年の右手が、刀の柄にかかり、鯉口を切ったのである。男を斬るつもりだ。
相手は傘を右手に持っている。すれ違いざまに斬りつければ、驚きあわて、刀を抜くのが遅れるかもしれない。それを狙っているものか……。
少年はこの男を待ち伏せしていた。おそらく遺恨があるのだろう。
ひょっとすると、誰かの仇を討とうとしているのかもしれない。だが、助太刀がおらぬということは、正式な仇討ではない。少年が見事本懐を遂げたとしても、罪に問われてしまう。
それに、いくら不意を突かれても相手は大人だ。普通なら少年を造作なく斬るであろう。
どんな仔細があるかは知らぬが、むざむざ少年を死なせるわけにはいかない。止めねばならぬ。
だが、いったいどうやって? 大悟は必死に考えた。少年が抜刀してからでは手遅れになる。
傘を放り出し、少年に向かって駈け出しながら大悟は大声で叫んだ。
「音次郎! こんなところで何をしておる!」
振り向いた少年の顔は真っ青で、くちびるをかみしめている。状況がわからず混乱している様子の少年に、大悟は飛びつき、うしろから抱きすくめた。
「放せ! 人違いだ!」
大悟は、逃れようと暴れる少年を地面に押し倒して覆いかぶさった。
「寝ぼけたことを申すな! この雪の中、さんざん探し回ったのだぞ! 叱られたくらいで、飛び出すやつがあるか! 父上には俺が一緒に謝ってやるから、もう意地を張るのはよせ!」
「反省文」柿村将彦
まあいいです。書きます。明らかに馬鹿げた枚数とわかっていながら、しかしそれを黙って受け取った以上、私は責任をもってこのとち狂った枚数分だけ反省文を書いてみせます。書いてみせますが、どうせ先生はこれを読まないんでしょう。だったら私も真面目には書きません。
お読みにならないことを前提に書くので、少々ふざけているように見える態度をとることもあるでしょう。非常識な枚数を書ききるために無駄話を挟んだり、露骨な字数稼ぎをすることがあるかもしれません。でもまあ構いませんよね? 反省文とは反省するための文章のことなのであって、謝罪文でも誰かに許しを請う文章でもないんですから。たとえどんな態度で何を書こうと、そこで反省が行われていさえすれば、それは反省文と名乗って間違いではないでしょう。そこは心配しないでください。この文章において、私は確実に反省します(多少それ以外のこともするかもしれないというだけで)。でもまあ先生にとってこれは一種の刑罰みたいなもので、無意味な文章を書かせるという一種の苦行を強いること自体が目的なのであり、そこに何が書かれてあるかなど二の次でしかないんでしょうから、別に何がどう書いてあろうが知ったこっちゃないですよね。何か文字が書いてある原稿用紙を提出さえすればそれでいいんですもんね。ちょっと喉乾いたのでお茶飲んできますね。
飲んできました。
さて。ではこれから反省のために、どうして私が遅刻をしたか、そしてなぜあんなヨレヨレのTシャツと半パン姿で学校に来ることになったかについて説明します。
が、先に述べた通り、すでに私はそれを詳しくお伝えしています。あれだけ何度も口頭で説明したことを再び書面で繰り返すのはいかにも馬鹿げているように思えますが、でもまあそれも仕方ありません。私の説明を何度も何度も聞いた上で、それでなお反省文を書くように言ったのは先生なんですから。それに、反省のためには自分のしたことを正確に思い出す作業が欠かせません。その上でああすべきだったとか、あんなことはすべきではなかったとか、それを考えるのが反省というものでしょう(たぶん)(知りませんけど)。
では説明します。
今朝、私はいつも通りに六時三十分の目覚ましで起床し、いつも通り身の回りの準備を済ませて朝食を摂り、そしてやはりいつも通りに七時二十分頃に家を出ました。先生は「寝坊したんやったら正直に言え」としつこくおっしゃいましたが、誓って私は寝坊などしていません。それは母に訊けばすぐにわかることです。なんなら小倉さんに訊いてみて下さい。小倉さんというのは私が登下校時に通る鞠葉の商店街の薬屋のおじいさんのことで、今日も通り掛かりに朝の挨拶を交わしました。耳はかなり遠くなっているみたいですが頭ははっきりしているので、今朝のこともちゃんと覚えているはずです。
商店街を抜けた私は路線バスに乗り、学校最寄りの印在寺の停留所で降りました。先生もよくご存知でしょうからこんなのはいちいち書くまでもないことですが、念のためと字数稼ぎのために説明しておくと、印在寺のバス停から学校までは国道をまっすぐ歩いて十五分ほど、距離にすると一キロちょいの道のりです。運行表通りなら私の乗ったバスは七時五十二分にバス停に到着しているはずですので、いかにゆっくり歩いたとしても、八時二十分の予鈴には充分間に合います。
ですがご存知の通り、結果として私は遅刻をしました。
一体どうしてか。
それは蓬辻の交差点に、でっかい荷物を持ったおばあさんがいたからです。
おばあさんのいでたちを詳しく言うと、まず和服。着物です。からし色というんでしょうか? それに細かい赤い筋がまばらに入った着物を着て、深い紫色の上着を羽織っていました。私は和服についてあまり詳しくないので正確なところはわかりませんが、とにかくそんな格好です。荷物は風呂敷。そんないでたちの、年の頃なら八十は優に越えているだろう誰の目にも明らかなおばあさんが、交差点の北東の角に立っていたのです。
「ブランコ」藤田雅矢
郵便ボックスだけでも三十二鉢もあるのに、さらに足もとにはボックスに入りきらないゴーラムや丸サボテンなどが、似たような小さな植木鉢に植えられ、ぎっしりと並んでいる。よほど多肉植物好きなのだろう。
そして、家の玄関の扉には「新みらい創造研究会」という看板がかけられていた。
「新みらい……」
看板はともかく、三十二個の植木鉢が並ぶ郵便ボックスがとても気になって、次の日から仕事に行くときに少し回り道をして、その家の前を通ることにした。そこには、ブランコが来ていた。なにか気に掛かっているのだろうか、植木鉢のそばへと尻尾を立てて歩いて行く。そのとき、どこか違和感を感じた。
植木鉢の並びが、昨日と微妙に違っていたのだ。
立ち止まってじっと見ているのも怪しいので、「ブランコ」と呼びながら鉢植えの並びをさっとメモにとった。グリーンネックレスは「グ」、ゴーラムは「ゴ」、アロエの「ア」、丸サボテンは「○」、オブツーサの「オ」。そして「豆」が銀杏の豆盆栽。ボックス毎に二鉢ずつが四つ。それが四段。
一段目:グ○ アア ○ゴ ゴグ
二段目:○ゴ グア ゴゴ ○ゴ
三段目:○オ ○豆 アグ ゴオ
四段目:ゴグ グア ○ゴ ○グ
ひときわ目立っていた銀杏の豆盆栽が、郵便ボックスから足もとへと移動し、代わりに三段目はゴーラムが横一列に並ぶ配置となった。なにかある。
「3つの生け簀」堀川アサコ
結局、最終電車で帰ることになった。どんなに夜遅くなっても、安藤さんを訪問しようという決意は揺るがない。それでいて、いよいよあそこに帰るのだと思うと、心臓が縮みあがるような気持ちになった。無意識のうちに、奥歯をかみしめている。定期券を買うのは億劫なので昨夜や今朝と同様に切符を買ってホームに向かった。
大粒の雨が線路を洗っていた。
乗りたくないのに電車が来る。着きたくないのに、アパートの最寄り駅に付いてしまう。
駅舎を出た途端、パンプスの中は水浸しになった。荒人川が暴れていた三百年前の壮絶な景色が、ふと脳裡に浮かんだ。助かろうとしてもがく捨彦を、大勢で押さえて川に沈める人たちの姿が見えた気がした。
呼吸が苦しいほどの雨の中、持っていても意味をなさない傘にしがみついて、懸命に歩いた。安藤さんに会いさえすれば、きっと適切なことを云ってもらえる。そうすれば、何もかもが解決するのだと、ひたすら胸に繰り返した。
右足、左足、右足、左足。一歩進むだけでも苦しい雨の中、その足が止まったのは、もう見慣れたはずの夜が、常とは違っていることに気付いたからだった。
灯りがない。
街灯も家々の照明も、一つも点っていないのである。
それでも、周囲は不可解な銀色の光でけぶっていた。それは雨が発する光にも見えた。いや、荒人川の川面の、あの銀色の輝きと同じ色をしていた。
その光に漠然と照らされ、押し合いへし合いする大勢の人影が、まるで騙し絵のように出現する。
その人たちは、友美の住むアパートの暗い階段から湧き出るように現れた。うごめく闇の塊のように見える人たちの中心に、友美は安藤さんの姿を見出した。
「紫には灰を」勝山海百合
横浜税関から連絡を受けた二週間後、鱗雲の浮かぶ秋の午後にアンヘリナは製鉄所や倉庫が立ち並ぶ港湾地区にある横浜税関川崎検疫所川崎支所に荷物を受け取りに出かけた。三週間のうちに送り主の履歴を調べ、心はずいぶん落ち着いた。小学校の同級生は、惑星ガーデニアに農業技師として入植していた。日本の大学でイネ科植物の研究で学位を取り、種苗会社に就職、種苗会社から宇宙へは、距離の飛躍はあるが地続きで胸に落ちた
現在の火星の住民は、多くが鉱山会社の労働者と宇宙港の職員だが、火星の食料問題はガーデニアが解決したと言われている。木星と火星のあいだのワームホールを使えば、火星とガーデニアは地球よりもずっと近い。
天井の高い倉庫に付随した受付で身分証明書を提示する。アンヘリナが壁のポスターを眺めて待っていると、背は低いががっしりした体軀の制服の係員が段ボール箱を一つ運んできて、カウンターに置いた。
「ご確認ください」
見ると乾燥した濃い紫色の根が詰まっており、アンヘリナは紫根が漢方薬でもあることを思い出す。乾いた植物の匂いがしたが、紫草特有と言える匂いかはわからなかった。真空パックされていたものを開梱、遠心分離器にかけて土砂を分離し、寄生虫やバイラスの検査をし、すべて検出されなかったので受け渡すことになったと告げられた。
「検査で重量がやや減りました。ご了承を」
受領書に固有署名を送信しながら「天使の分け前ってとこね」と呟く。
持ち上げると紫根の入った段ボールは思ったより軽かった。駐車場の近くに生えている薄(すすき)が穂を出し始めていた。
「サナギ世界」関俊介
1 コガレ『イサへ』
わたしたちはかつてヒトと呼ばれていた。
どうしようもなく繁栄して、自分じゃ制御できないぐらいの栄華を誇って、あるときを境にこの星の歴史から忽然と姿を消してしまった。神さまだかに怒られてその姿と生きかたを変えさせられたとか、偶発的な要因で変異してしまったとか、ヒトであることに飽きたなんて説もあるけど、理由はともかく、ヒト種が分化してできたのがわたしたち。
二本の腕に二本の脚。ヒトの面影を残しつつ分化したヒト派生種には、わたしたちの他にアリとかセミとかカマキリがいる。それぞれが自分たちに合ったクチクラを着て、自分たちなりの方法でこの世界で生きている。わたしたちはバッタ。脆弱でちっぽけなバッタ。ただのイナゴちゃんというわけ。
それで、あんたが知りたいのはなんだっけ。胸がうずいてやまない、言葉にできない感情のことね。無知きわまりないあんたに、このわたしがきちんと教えてあげましょう。それはね、恋というのよ。いったい誰に恋をしてしまったのやら。この群れであんたが恋をしそうな子。あんたの好みはわかっている。かわいくて優しくて、いい匂いがして、思わず抱きしめて守ってあげたくなるような子。かぎられてくるね。というか、そんな子、いる?
そういう表面的なものじゃない? もっと奥底から沸きあがってくる? あんた、恋を軽視しているでしょう。恋というのは、体のいちばん奥から溶岩のように噴きだす、生存の原動力なのよ。夏に生まれて冬に死んじゃうわたしたちは、短い一生のすべてを恋にささげるよう義務づけられているの。それを否定するのは種の維持と繁栄を否定することになるのだけど、そういうことじゃない? しょうがないな。何も知らないあんたのために大事なことを教えてあげよう。あんたはね、虚しくて寂しいの。満たされていないの。だから心にぽっかりと穴が空いているの。なぜ寂しいと感じるのかって? 答えは簡単。
わたしたちが黒いバッタだからよ。
ほら、見て。あの空。あの黒い塊。ぜんぶバッタだよ。あんたの寂しさが呼び寄せちゃったのかな。それにしても大群だね。あの黒い粒のひとつひとつがわたしたちと同じバッタなんだね。あんな群れにいたら虚しいなんて言っていられないかもね。わたしたちが黒バッタとして生まれたのは、群れになるため。ああなるのが自然で、必然なの。
イサ、あんたもあんなふうになりたいんでしょ。
プロフィール
小田雅久仁 おだ・まさくに
昭和四九年、宮城県仙台市生まれ。関西大学法学部政治学科卒業。現在、大阪府豊中市在住。二〇〇九年『増大派に告ぐ』で第二一回ファンタジーノベル大賞を受賞し、デビュー。二〇一三年『本にだって雄と雌があります』でTwitter文学賞国内部門受賞。三作目の『残月記』で二〇二二年に吉川英治文学新人賞、二〇二三年に日本SF大賞を受賞。二〇二三年七月に怪奇小説集『禍』を刊行。
粕谷知世 かすや・ちせ
ずっと、通勤・通学とは無駄な時間の最たるもの、と思っていましたが、一人で本を読み、考えごとにふけることのできる贅沢な時間でもありますね。自動的にウォーキング時間もとれるし。最近は歴史系の長篇(平安時代!)に取り組んでいますが、掌篇、短篇もぽつぽつ発表しています。どうぞ、よろしく!
X(ツイッター):粕谷知世のクロニカ【記録】@Chise_KASUYA
西崎憲 にしざき・けん
翻訳家、作家、アンソロジスト。訳書に『郵便局と蛇』コッパード、『ヘミングウェイ短篇集』、『青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集』(亜紀書房)など。著書に第十四回ファンタジーノベル大賞受賞作『世界の果ての庭』、『蕃東国年代記』『未知の鳥類がやってくるまで』『全ロック史』『本の幽霊』など。フラワーしげる名義で歌集『ビットとデシベル』『世界学校』。音楽家でもある。
日野俊太郎 ひの・しゅんたろう
二〇一一年『吉田キグルマレナイト』で第二十三回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞。青春時代を謳歌した京都を離れ、湖国に移り住むこと早ひと回り。土地に古くから根付く数々の物語の種に心ときめく毎日。
南條竹則 なんじょう・たけのり
山形の温泉と東京を往復の日々。アーサー・マッケンの自伝を翻訳中。
冴崎伸 さえざき・しん
児童文学に挑戦しています。この漢字は使っていいのか、この言葉はわかってもらえるのかと、悩むのが楽しいです
北野勇作 きたの・ゆうさく
一九六二年生まれ 大阪在住 小説家
『ありふれた金庫』『かめくん』『どろんころんど』等、亀や狐や狸や泥を材料にしたSFを書いてます。
ツイッターで継続中の【ほぼ百字小説】が、四〇〇〇篇を超えました。生きている間にどこまでいけるんでしょうね。
石野晶 いしの・あきら
一九七八年岩手県生まれ。二〇一〇年『月のさなぎ』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞。著書に『水光舎四季』『彼女が花に還るまで』『やがて飛び立つその日には』など。虫好きの息子のため、この秋はカマキリを飼い、エサ探しに明け暮れた。現在カマキリの卵と同居中。
大塚已愛 おおつか・いちか
日本ファンタジーノベル大賞二〇一八と第四回角川文庫キャラクター小説大賞を同時受賞、新潮社より『鬼憑き十兵衛』 KADOKAWAより『ネガレアリテの悪魔』シリーズを刊行。ノベリズム大賞受賞作『Nostalgia』連載中。
久保寺健彦 くぼでら・たけひこ
二〇二一年に『青少年のための小説入門』が集英社文庫から刊行され、現在、次の長編にとり組んでいるものの、核となるアイデアが見つからない。昔、どこかで見かけたような。ちょっとさがしに行ってきます。思いがけず遠出して、帰りが遅くなるかもしれません。
森 青花 もり・せいか
一九九九年「BH85」にて第十一回ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞、デビュー。
二〇〇三年「さよなら」を角川書店より上梓
趣味は俳句と写真撮影です。花や猫を撮っています。
ラグビーや芝生は緑空は青
ほととぎす乳房も灰になりゆくか
斉藤直子 さいとう・なおこ
二〇〇〇年『仮想の騎士』で第十二回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞。≪惑星と口笛ブックス≫より同書電子版(二〇一八年)、短篇集『ゴルコンダ』(二〇一九年)。今回の作品はコロナ禍の備忘録のような実録のような。モチーフはエッシャーに描いてもらいたい落語第一位(自分調べ)の「あたま山」です。
三國青葉 みくに・あおば
二〇一二年『朝の容花』で第二四回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞。『かおばな憑依帖』と改題しデビュー。神戸市出身、徳島県在住。真面目なSFファンだったのですが突然時代劇にハマり、それが高じて時代小説を書いています。最近の著作は『損料屋見鬼控え』シリーズ、『福猫屋』シリーズ(共に講談社文庫)など。猫様の下僕と兼業です。
柿村将彦 かきむら・まさひこ
先日初めて競馬場へ行ったのですが、「走れ!」とか叫んでいる人が沢山いてびっくりしました。一体どれだけ金を賭ければ馬が人語を解すると思い込むまで錯乱できるのでしょう。その日は全部で五百円賭けて三百円勝ちました。やったあ?
藤田雅矢 ふじた・まさや
一九九五年『糞袋』で第七回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞。受賞作は≪惑星と口笛ブックス≫より復刊、また短篇集『植物標本集(ハーバリウム)』など電書オリジナルで配信中です。園芸書『捨てるな、うまいタネNEO』もあり、植物を愛でていじります。今回の作品は、路上園芸SFでもあります。マイクロノベルと画像のnoteを始めました。https://note.com/fujitam3/
堀川アサコ ほりかわ・あさこ
第十八回日本ファンタジーノベル大賞(二〇〇六年)/優秀賞『闇鏡』でデビュー。
青森市在住。深海生物と多肉植物の変なフォルムを愛しております。深海生物を飼う技量がないので、多肉植物を窓辺に並べ、ニヤニヤする昨今です。
勝山海百合 かつやま・うみゆり
最近の仕事は『NOVA 2023年夏号』(河出文庫)掲載の「ビスケット・エフェクト」と『幻想と怪奇 ショートショート・カーニヴァル』(新紀元社)掲載の「あかつきがたに」です。新刊鋭意執筆中。
ブログは「鳥語花香録」
ツィッターは@UmiyuriK
関俊介 せき・しゅんすけ
『ワーカー』にて第二十四回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。アンソロジーだとわかっていながら長編を送りつけてしまう不届きな物書きがこちらです。今は世に出せるかどうか未定のまま、幽霊なんていないと言いはっていた母親が幽霊になって現れたなどという物語を、衝動と創作意欲だけを燃料に執筆中。近著は現代に生きるシノビの、書きすぎなくらいに書ききった活劇『精密と凶暴』(光文社刊)。