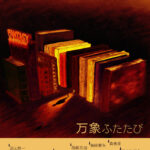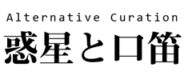キラー・拓くこと
南インドの武術からはじまる岡田麻沙の世界への興味は言葉やデジタル技術へと広がり、ブンゲイファイトクラブ(BFC)の第4回では水際立った修辞力、分析力で決勝ジャッジとなった。
『うか 岡田麻沙作品集』は初の小説集。「うか」「等高線のシアン」「星座落ち」の3篇を収録。
文字を作る会社に勤務する人物を敬体で描いた「うか」は不可思議な作品で、今後著者が書くことになる秀作名作の質を保証するようなキラーストーリーである。
「等高線のシアン」でも言葉は重要なモティーフであり、肩甲骨のあいだに生える植物や、並行して語られる詩人との関係、そしてふたりの歩く町が魅力的に語られる。
「星座落ち」はどことも知れない町、土地を舞台に、空想や夢のような素材で織られたタピスリーである。不可知と陶酔をふくんだ実験作でもある。アリとナシの姉妹が印象的である。ナシは時折消える。
3作から感じ取れるのは優れた書き手がもつべき胆力で、背景には暴力のエコーがかすかに響いている。岡田麻沙はおそらくなにかを殺すために文芸の世界にやってきた。
表紙イラストレーションとブックデザインはやすだゆみ。400字詰め原稿用紙換算約85枚。価格500円。
「うか」 抜粋
いまの部署へ異動になったのは、昨年の暮れのことでした。辞令が張り出された日は、廊下ですれ違う社員から次々と声を掛けられたのを覚えています。おめでとうと言ってくる人もいましたし、これからは楽になるなと口にする人もいました。うまく逃げおおせたな、なんて囁いた上司もいて、思わず笑ってしまいました。みんなの反応はもっともです。その前の三年間、「にすい」を削りつづけていたことを思えば、飛躍的な昇進といえたでしょう。
にすい班の作業部屋は狭いうえに寒く、誰も行きたがりませんでした。社員三名がようやっと立ち回れるほどのスペースで、常時二台のガスストーブが燃えています。それでも、月に一度は誰かが軽度の凍傷になります。にすいの寒さは、皮膚の内側に凍みつくのです。あの班に長くいる人間の表情は強張っています。班長のIさんは色の白い小柄なひとで、ごく薄く、ナイフでそっと撫でたような法令線があります。溝の中まで、きっぱりと白いのです。
うかんむりの部屋には大きな台が五つあり、それぞれに五、六人が就いて作業をします。みな好き好きの文字を削ります。異動の初日、人数の多さにも部屋の大きさにも驚かされましたが、何よりも当惑させられたのは、汗ばむほどの室温でした。一台きりのエアーコンディショナーが吐き出す温い風は文字の削りカスを間断なく舞いあげており、七十平米に満たぬ室内は、全体に靄がかかったように白んでいました。入室して数分と経たぬうちに、自分の皮膚が取り返しのつかない形で汚れてしまったように感じました。
「等高線のシアン」 抜粋
ふたりで低地を散歩するのは、ちょっとした冒険だ。傾斜の急なエリアではたまに言葉崩れが起きる。坂の途中に堆積した言葉が、ある瞬間に踏みとどまれなくなり、土砂崩れのように滑り落ちてくる。言葉のかたまりは人にぶつかると、そのまま内側をすり抜ける。皮膚を引っ搔かれるような感じ。愉快な体験ではない。詩人のように、大規模な言葉崩れに直撃され、性質が変わってしまったものもいる。
町の底では、重なり合った言葉がめり込んで、道路のそこここにひび割れを生んでいる。いまのところ、いちばん大きな裂け目は五十メートルほど。低地の奥を南北に走る。この傷口はフォトスポット化しており、撮影のベストポジションを示す案内板や、観光客が深部に近づきすぎないよう見張るためのスタッフ、数年前から出現したコーヒースタンドなどで賑わっている。
堆積し、滑り落ちてくる言葉のせいで、低地では産業が発達しない。主な収入源は観光客だ。かれらは高地の宿から直通で出ているマイクロバスに乗って最底部にやってくる。一杯四百五十円の粉っぽいカフェラテを飲み、遠巻きに底を眺め、写真を撮り、三十分と経たぬうちに引き返していく。
たまに観光客に混じって遊ぶ。「気焔万丈」とか「鬱勃」とか「大車輪」とか、重量級の言葉を見つけてはスマホで撮影する。どうせ見返すこともないくせに、と詩人が腐す。彼女の足さばきはあまりに見事で、土地の人間であることが、ひと目でわかってしまう。
「星座落ち」 抜粋
スナが十五歳になる頃までは、港町でツノザカナがよく捕れた。死んだツノザカナは日光に当たるとたちまち溶けて、白くすべすべしたツノを残す。これを夜の海に沈めると、水面に映像が現れる。
液体でつくられた都市。月面を埋める何千もの墓。空に向かって落葉する紅葉と銀杏。スイカ柄の地平線。鯨の背中で栄えては消えてゆくいくつもの小さな文明。球体のオーロラ。
町の人々はこれらを、ツノの見る夢だと考えていた。
満月の夜は家を抜け出し見に行った。母は女たちから命を取り出すという使命に忙しく、悪い娘のことなど気にかけなかった。明るい夜、港に集まる人々の顔にはみなどこか似たような表情が浮かんでいる。荒っぽい海の男たち、子ども嫌いの女、一人暮らしの青年。旅人。
またあんたかい、と呆れながら男たちはスナを出迎える。もう少ししたら始めるよ。大きな掌の上で白いツノは乾いた音を立てる。かれらの目は色を隠さない。まだ少女のはずのスナを見て、「いい女」だと誰かが言う。
「いや」スナは首を振る。そうじゃなかった。
「悪い娘だってさ」母はいつもそう言った。男たちは一斉に笑う。
「いい女は、悪い娘なのさあ」
酔っ払った一人が歌うように言い、潮風でねばつくスナの肌を目で舐める。母がサンバだから、その娘がヨウフになったんだろうと男は続ける。旅人が心配そうに目配せをする。その目の奥にも同じ色がある。
海に落とされたツノが水面に光彩を放つ。楕円状の白い光は径を広げながら、沖に向かって伸びてゆく。四畳ほどの大きさになった頃、むくりと像が立ち上がる。
巨大な光のムカデが姿を見せた。夥しい数の脚が夜を引っ搔き、ゆっくりと上昇していく。暗い雲のふちに頭が消えても、尻尾はまだ海上に現れない。「親切」な荒くれものの一人が、隣に腰掛け、髪や首筋を撫で回してくる。「こういうことは」耳元に唇を押し付けて囁く。
「考えないほうが上手くできる」筋肉に覆われた太い腕は闇の中でも、よく日に焼けていることがわかる。
母は気まぐれに帰ってきた。一つの季節に一度。港町は、盛りを迎えた他地から逃れる先としては最適だったのだろう。
「アリ、ほら。お姉ちゃんがきたよ」
虚空を指差す。母には消えているナシが見えるらしかった。
「アリ、アリ。お姉ちゃんも一緒に行くって」
日焼けした顔を歪めて笑い、見えぬ姉と言葉を交わす様は恐ろしかった。怯えるアリの様子を見ると、さらに笑った。二、三日、わが子のそばをうろつくと、また荷物をまとめて去っていった。
まれに、母の行方を追う恋人たちが助産師の家を訪ねてきた。思い詰めた表情の青年や、蔦模様のシャツに身を包んだ、信じられないほど粘着質な男。何度会ってもどうしても顔を覚えられない無口な旅人。男たちはみな、ナシの姿を見ると目に色を宿すのだった。
そういうときのナシは消えない。外側にグッと力を入れて、黙って立っている。それで助産師は、腰が痛いときの顔になる。
週末になるとアリはよく友人らと街へ遊びに出かけた。ある午後、雑貨屋にツノザカナのブレスレットを買いに行く約束をした。港町で捕れる白いツノは、恋愛成就のお守りとして少女たちに人気があった。
ナシを連れて行ってもいいか尋ねると、みな一様に言葉を濁した。
「ナシちゃんはちょっと」目配せをし合う。
「街で消えたら大変だし」「ね」口々に同調する。
「それに」声は粘り気を帯びてゆく。
「ナシちゃんなら、お守りなんかなくても大丈夫でしょ」
ヘエ先生がいなくなってから、ナシの消える時間はどんどん長くなっていた。たまに帰宅すると、その体からは濃い潮の匂いがした。
プロフィール
岡田麻沙(おかだ・あさ)
山口県生まれ。テクストと身体との関わりに関心があり、大学・大学院で南インドの武術についてフィールドリサーチを行う。その後、時間に埋め込まれたテクストへの興味から、チャットボットやロボットの会話体験設計に携わる。デザイン会社での企画・ライター職を経て、フリーランスに。インタビューやコラムの執筆に加え、UXライターとして、デジタルプロダクトにまつわる言葉のルールを設計している。
こうした取り組みの傍らで、家畜化される以前の文章が読みたくなり、物語らしきものを書き始める。ブンゲイファイトクラブ4最終ジャッジ。