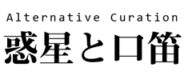シングルカット第8作。
「あまたの叉路の庭 El jardín de senderos que se bifurcan」は、短篇集 Ficciones (『伝記集』)に収録されたホルヘ・ルイス・ボルヘスの代表作のひとつであり、ボルヘスの文学的態度が集約された一篇でもある。
ボルヘスの英語圏への紹介は、アントニー・バウチャー訳の本作が嚆矢で、掲載は『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』1948年8月号であった。
短篇小説の到達点のひとつと目される。
初出は『文学ムック たべるのがおそい』vol.6 書肆侃侃房。
400字詰原稿用紙換算訳30枚。
ホルヘ・ルイス・ボルヘス Jorge Luis Borges(1899-1986)
アルゼンチンの詩人、翻訳者、アンソロジスト、作家、図書館館長。最重要の文学者の一人。
抜粋
一瞬、絶望から絞りだした計画をリチャード・マッデンが見抜いたのではないかという考えに囚われた。けれどすぐそれは不可能だと考えた。つねに左に曲がれという助言から連想したのは、それが迷路の中心の広場に到達するための一般的な解であるということだった。迷路については少しばかり知っている。わたしは雲南省の知事であったテュイ・ペンの曾孫なのだからそれはゆえないことではなく、かれは『紅楼夢』より登場人物の多い小説を書くために、そして人のことごとくが迷う迷路を造るために、いっとき権勢を放棄したのだ。十三年のあいだテュイ・ペンは様々な種類の努力をそのために捧げたが、どこからかやってきた者に殺されることになったし、小説はばかげたものであり、誰も迷路を見つけることはできなかった。イギリスの木の連なりの下でわたしは失われた迷路のことを考えた。侵害されることなく、完璧な姿を保ち、人間の知らない山の頂に広がるそれを想像した。水田や水路に変じてしまったものを想像した。無限であることを想像した。八角形の四阿や曲がりくねった小径ではなく、川や省や王国からなる迷路……。わたしは迷路のなかの迷路のことを考えた。入り組んだまま成長する迷路、過去と未来を含み、いくつかの星まで含む迷宮。そうした幻影に気を取られて、わたしは追われているという自分の運命を忘れた。どのくらいのあいだだったか、この世界を抽象的に理解したと感じた。霞んでいるが生彩に富んでいるようにも見える野面、月、残光がわたしの内側で存在を主張した。それに下り坂なので疲れるということもなかった。宵は親密で無限だった。すでに滲みはじめた草地の上を小径は縫うように延びて岐れた。高音の旋律が風の往来に従い、近づき、去り、それは葉擦れの音のせいで、そして遠方からやってくるせいで、くぐもっていた。ある人間が誰かの敵になったり、べつの機会にさらにべつの誰かの敵になったりすることはあるだろうと思う。けれど、ある国家の敵になることはできない、蛍や、言葉や、庭や、水路や、西風の敵になることはできない。そんなことを考えているうちに、わたしは錆の浮いた大きな門の前にいた。鉄の柵の向こうに並木道と四阿があるのが見えた。すぐにわたしはふたつのことを理解した。ひとつは些細かつ驚異的なものだった。音楽は四阿からやってきたもので、しかも中国のそれだった。だからわたしは十全に受けいれていたのだ。なんら身構えることなく。鉦があったか、呼び鈴があったか、それとも手で扉を叩いたかについては記憶がない。音楽は火花のようにつづいていた。