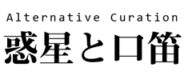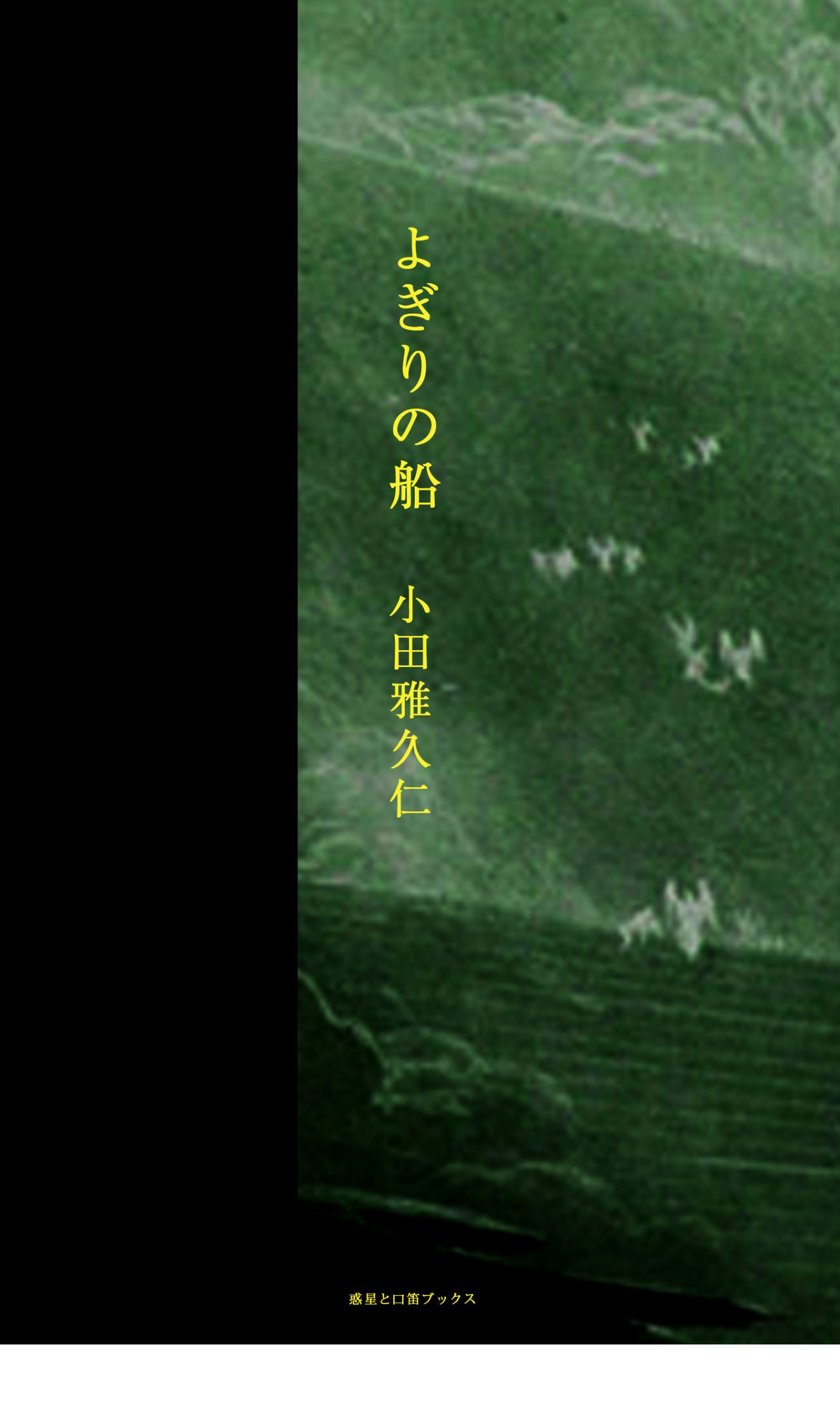
本書は2018年に刊行された我が国史上最大のファンタジーアンソロジー『万象』のなかの1作です。『万象』をお持ちのかたは購入する必要はありません。
『万象』は『SFが読みたい! 2020年版』の2019年国内ランキングで28位になりました。そのなかから創元SF文庫の年刊傑作選『おうむの夢と操り人形』に2作再録されていますが、編者のひとり大森望氏がもっとも収録したかったのはこの「よぎりの船」でした。しかし120枚という長さのためにその希望は叶えられませんでした。
「よぎりの船」はおそらく21世紀になって書かれた幻想文学のなかの最高ランクに属する作品です。幻想の質、スケールの大きさ、筆力、それらが相乗効果を生み、驚嘆すべき高みに至っています。幻想文学の愛読者の多くはこの作家、この作品を愛するでしょう。海外幻想文学と国内幻想文学をリンクするような作品でもあります。英語圏に紹介されれば幻想文学関係の賞を受賞するのではないかと推測されます。
ふたつの頭、よっつの眼を持つ鳥に魅入られた男、日常に紛れこむ異様な存在たち、よぎりとはいったい何なのか。そして想像を絶する展開。
名作『増大派に告ぐ』『本にだって雄と雌があります』で小説の世界に大きな足跡を刻んだ小田雅久仁の空前の幻視に驚嘆してください。
表紙のミルトンの『失楽園』の挿画で、ジョン・マーティンの手になる版画です。
シングルカットシリーズ第8作。価格350円。
〈シングルカット〉は短篇小説をコーヒー一杯程度の価格で提供するシリーズです。
註
この作品は尋常の作品ではありません。読んだ者にあるいは累を及ぼすかもしれません。午前零時に合わせ鏡をしてはいけないように、雷が鳴るときに梯子の下をくぐってはいけないように、慎重なかたはこの作品を避けるべきです。以下の抜粋に目を通すこともお勧めいたしません。
抜粋
一瞬、小太郎を置き去りにして、身も世もなく海のほうへざぶざぶと逃げてゆこうかという考えが兆したが、しかしすぐさまよぎりの四本の腕がこの頭を押さえ、海に沈める光景がそれを塗りかえた。孝彰はいよいよどうしたらいいかわからず、ただ顔を伏せ、杭にくくられたみたいに手もなく立ちつくしていた。血の気が引き、学校に遅刻したときみたいに、小便が漏れそうな切迫感がきゅうと突きあげてくる。エツから聞いた曾祖母の話が思い出された。目が合うと連れてゆかれるというのは本当だろうか? 涙をこぼすと見のがしてもらえるというのは本当だろうか?
横目であたりをうかがった。夕陽を呑みこんだばかりの黒い山並み、残光に染まるまばらな雲、右を見れば、散歩者たちがのんきに堤防沿いの遊歩道を歩いていた。左を見れば、生ぬ るいような波がとぷりとぷりとうねっていた。何喰わぬ顔をした確かな世界に囲まれていたが、二人のよぎりが近づいてくるのもそれ以上に確かな現実だった。小太郎が右に左に小刻みに跳ねながら、よぎりに向かって吠えだした。しかしやはり怯えがあるのか、きっと噛みついてやるという前のめりな吠え方ではなく、どこか腰の引けた身の運びだ。
二人のよぎりは、小太郎の虚勢に気圧されたわけでもなかろうが、こちらを避けるように左右にじわりと距離をひろげた。孝彰にできることと言えば、ただもう石みたいにうつむいて、早く行け、このまま通りすぎろ、と祈りながら身を固くすることだけだ。よぎりは足音もさせず、そよ風になびくレースのカーテンのようにふわりふわりと浮き加減に足を運んできた。双頭の鳥は幼い孝彰の視線を認めてこちらを睨みつけてきたが、二人は孝彰と小太郎の存在に気づきながらも、もっと深遠な憂いに心を囚われているかのような鈍い足どりをゆるめることなく、そのまま通りすぎてゆきそうな気配だった。
大丈夫だ、いける、と楽観が頭をもたげた瞬間、その頭を叩きつぶすように、二人が同時に立ちどまった。ちょうど孝彰と小太郎を左右から挟む嫌な立ち位 置だ。孝彰はぎょっとし、尻の穴に棒でも突っこまれたかのように縮みあがった。二人が足を止めたのは、孝彰たちに心をとめたからに違いない。視界の両はしに、たたずむ二人の姿が見えていた。一糸まとわぬ二人の裸体は、間近で見ると人肌らしいなめらかさはなく、全身に塗りたくった泥が乾いたようにざらついており、激しく躰を動かそうものならそこかしこにひび割れが走り、みるみる皮膚が剥がれ落ちてゆきそうだ。小太郎はいよいよ怖さをおぼえたと見えて、孝彰の脚に尻をすりつけだし、しかしそれでもときおりつぶてでも投げるように小さく吠えつづけていた。
(中略)
以来、孝彰はよぎりとのつきあい方を考えるようになった。よぎりは日暮れ時にもっとも濃くはっきりと見える。出会っても無理に避ける必要はないが、目を逸らしたまま立ちすくむのもまずい手だ。子供はただでさえからかわれがちだから、見えていると向こうに知れても、関わるつもりはないという強い意志をイバラのように張りめぐらし、気迫ではねつけねばならない。あの日のように小太郎が立ちどまって吠えたてても、ほかの犬と遭遇したときと同じように無理矢理にでも引っぱってゆく。夕暮れ時に出歩くのをためらう気持ちは長らく尾を引いたが、コツさえわかればもう怖くなかった。怖くなくなると、今度は逆にその逢魔が時を狙って出歩くようにさえなった。
歳を重ねるにつれて、よぎりとはいったいなんなのかという疑問はますます胸のうちで肥っていった。近所で見かけるよぎりは、みな東を目指しているようだった。家のすぐそばを臨港線と呼ばれる太い道路が走っており、そこでは見あげんばかりの巨大さのよぎりを何体も目にした。根を蠢かして歩く樹木のようなのも見たし、一軒家ほどもあるカタツムリのようなのも見た。さらには、背中に雑木林のようなものをこんもりと繁らせた、歩く古墳とでも呼びたくなるようなよぎりにも出くわした。道幅いっぱいにひろがり、身をおおう白い樹々を揺らしながら、やはり東へ向かって進んでいた。脚が幾対もある大亀のようでもあったし、長命の果てに育ちすぎたクマムシのようでもあった。ただただ唖然として見あげるほかない、荘厳とすら言える巨?だった。その巨大な姿を人間の乗る車がずぼりずぼりと呆気なく貫いて走り抜けてゆくのだ。子供の時分ほどよく見ると祖母から聞いていたが、運転する大人たちにはまるで見えていなかったのである。
しかし大阪の吹田市の大学に通いはじめたとき、初めて西へ向かうよぎりを見た。音楽サークルの仲間と金沢へ旅行に行ったときは南へ向かうよぎりを見たし、社会人になって千葉に出張に行ったときは北西へ向かっていた。静岡では北東へ、札幌では南へ、今治では東へ……出張や旅行でさまざまなところへ足を伸ばし、何体ものよぎりを目にしたが、彼らの目指す方角は土地土地でてんでんばらばら、全国のよぎりたちが聖地のようなある一点を目指して移動しているという子供のころからの推測は脆くも崩れ去った。