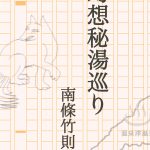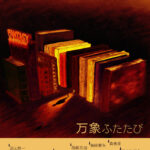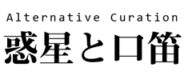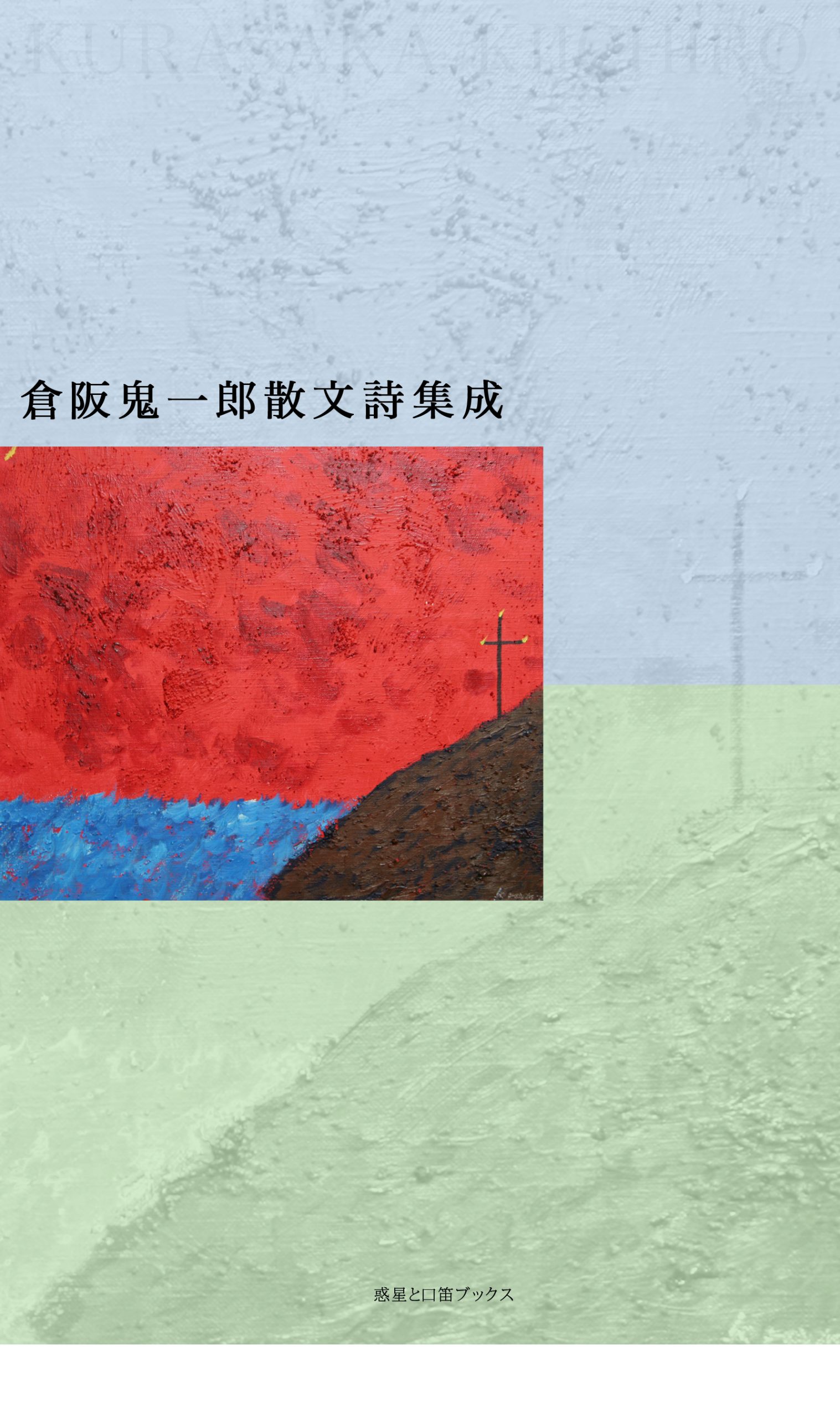
俳人、歌人であり、作家としては怪奇幻想、ミステリー、時代小説を書き、のみならず音楽を作り、絵を描き、マラソンやトライアスロンをたしなむ倉阪鬼一郎はまた刮目すべき詩人でもある。
本書はこれまで発表された三冊の私家版詩集『ふるふると顫えながら開く一冊の黒い本』『何も描かれない白い地図帳』『だれのものでもない赤い点鬼簿』を収録し、さらに書きおろしの詩集『世の初めから隠されていた三冊の画集』を加えた決定版といえるコレクションである。本書によって倉阪鬼一郎の詩におけるおそるべき達成を目の当たりにすることができる。
あとがきにおいて倉阪鬼一郎は以下のように記している。
最後に、「無人島へ持っていく作品を一冊だけ自作から選べ」と言われたら、私は迷わず小説ではなく本作を選びます(電子書籍なので端末ですが)。私のエッセンスはすべてこのなかに詰まっています。
本書は独創および博捜とたゆまぬ集中との賜物であり、詩才を与えられた者がゆっくりと歩くときどのような果 実が結ばれるかの好例であり、幻想と省察の悦ばしき結婚である。
400字詰め原稿用紙換算約230枚。表紙に使用した絵は著者の作品である。
価格は1000円。
ふるふると顫えながら開く一冊の黒い本 抜粋
うじうじと
うじうじと世をすねているうちに終末になった。
西の空に「おわり」と書いてあるから、今日が終末だとわかる。ああ、そうか、もう終わりなのか。そうだとわかっていたらあれもしたのに、これもしたのにと次々に思い浮かぶけれど、悔やんでも仕方がない。西の空に「おわり」と書いてあるから、今日が終末なのだ。
とうとう終末ですね、まいりましたね、と見知らぬ人が声をかける。ええそうですね、あそこに「おわり」と書いてありますね、と弱々しくほほ笑みながらわたしは答える。
そうこうしているうちにも終末は近づいてくる。「おわり」が赤く染まり、やにわに崩れたら終わりだ。本当に終末なのだ。
何か本当にやり残したことがあるような気もしたが、思い出せないからあきらめた。そして、もう一度西の空を見た。少し歪みはじめている「おわり」という字をぼんやりと眺めた。
うつうつと
うつうつと日々を過ごしていると召集令状が来た。
三回読み、五回読み、十回読んだ。読み返すたびに、それは召集令状として完璧な姿を整えていった。
わたしは、ああ、とため息をついた。なぜこの歳になって召集されなければならないのか、あまりにも理不尽だと思ったが、ひとたび召集されてしまったらもう逃げる手立てはない。
やむなく土手へ行った。よく晴れた日、同じように召集された者たちとともに、土手で一列になって体操をした。掛け声に合わせて腕や腰を回し、手を挙げて天を仰いだ。
それから、声援を送った。ここを通り過ぎているらしいものに向かって、精一杯の声をかけた。何が通り過ぎているのか、わたしの目には見えない。おそらくだれの目にも見えていないだろう。
とにかく召集されてしまったのだから、声をかぎりに叫んだ。力つき、周りでバタバタと人が倒れる。それでも懸命に叫んだ。がんばれ、がんばれと声を嗄らして叫んだ。
何も描かれない白い地図帳 抜粋
屋上
だれも入れない屋上に水槽がある。プラスチックの水槽だ。屋上のほぼ中央に、矩形の水槽がきちんと据えられている。
いつだれが、何のためにその水槽を置いたのかわからない。そもそも、階段のない屋上へどのようにして搬入したのか謎だ。
一度も水を注がれることなく、水槽は屋上で日に晒されている。あまりにも長く陽光に晒されすぎたから、水槽はもうぼろぼろだ。だれかがほんの少し触れただけで、おそらく崩れてしまうだろう。
しかし、屋上を訪れる者はいない。だれかの指が触れることはない。
だから、水槽はそこにある。屋上の中央で正しい矩形をとどめている。本当はぼろぼろになっているのに、完全無欠なふりをして虚ろを揺らしている。
だれのものでもない赤い点鬼簿 抜粋
運河の殺人鬼
運河の街で殺人鬼が生まれるのはよくあることだ。おそらくは霧の中から、殺人鬼は生まれる。もしくは、運河の泥水の中から這い上がってくる。
いずれにしても、彼は生まれながらの殺人鬼だ。この世界で目を開けたとき、すでにその手にナイフを握っていた。
刃先から血と水を滴らせながら、彼は運河の街を歩く。だれかが見た夢のように霧笛が響く晩、運河の殺人鬼はふと歩みを止め、風の中で目を瞠る。
何かを思い出してしまった彼は、自分が手にしていた物を見る。生まれたとき、すでに握っていた物を、ひどく不思議そうに眺める。
世の初めから隠されていた三冊の画集 抜粋
不完全な額縁
その額縁屋で売られているのは不完全な額縁ばかりだ。一つとして閉じているものはない。三辺が正確な直角を成していても、残りの一辺がない。額縁になりそこなったものだけがむやみに置かれている。
額縁屋は奥に長い。どこまで進んでも不完全な額縁が並んでいる。ただし、それがもはや額縁屋ではなく、洞窟の趣になってきたとき、売り物のたたずまいが変わる。それまでは不完全な三辺の額縁だったのに、いつからか一辺だけに変わってしまうのだ。
その一辺は、不完全な額縁のどれかに合致するだろう。おそらくは完成に導く鍵になるだろう。だが、いままで見てきた不完全な額縁があまりにも多すぎたから、額縁を完成させようとする意志を根こそぎ奪い去ってしまうのだ。
一辺を手に取った者はしげしげと見て、完成した額縁を思い描く。そして、ふっと一つ息をついて元の壁際に戻し、また暗い洞窟の奥へと進んでいく。