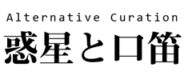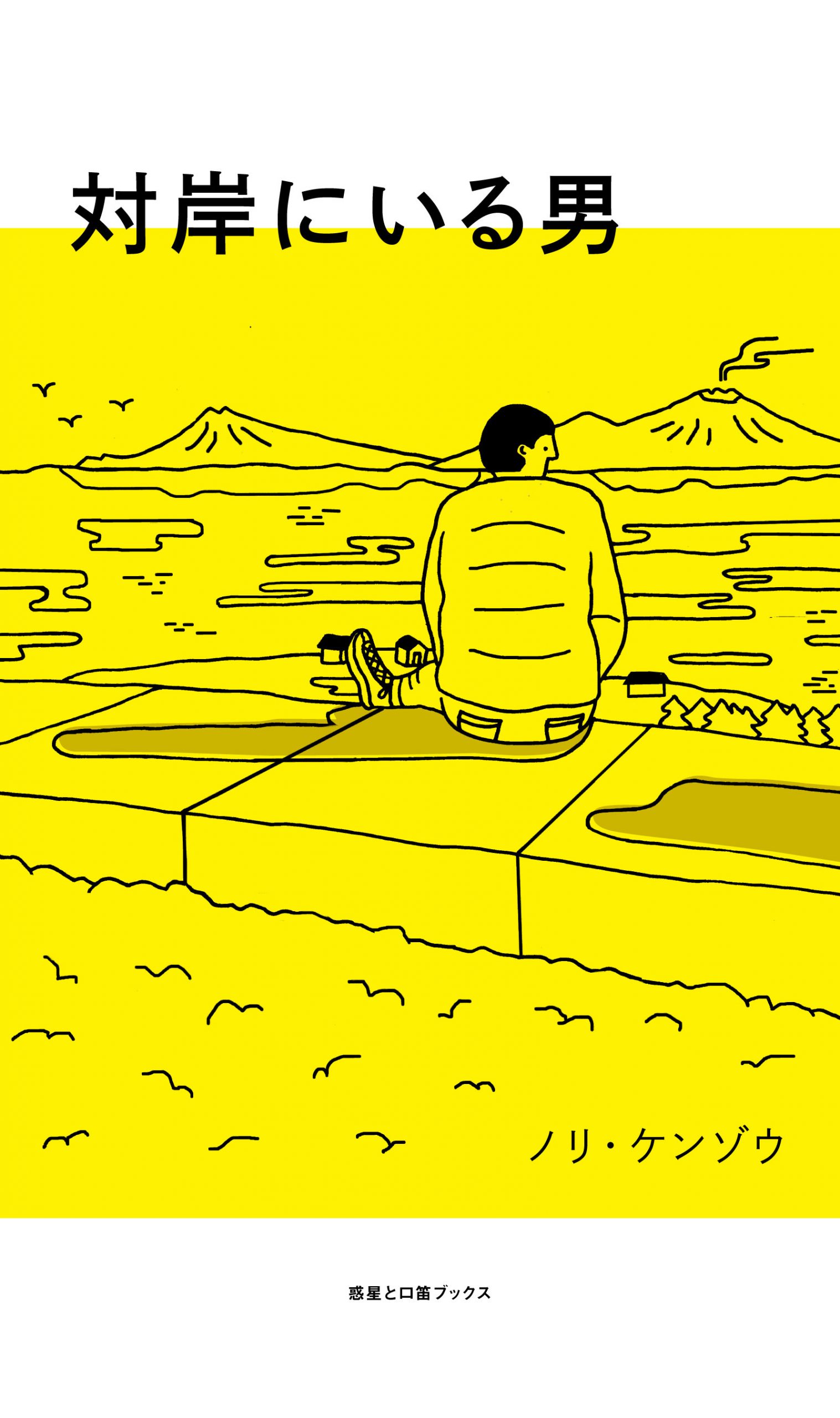
文体=スタイルこそが小説である。吉田健一、稲垣足穂、渡辺温、マルセル・ベアリュ、レオノーラ・カリントン、スティーヴン・ミルハウザー、かれらは質の違いこそあれ、いずれもみなスタイルにこだわりを見せた書き手たちである。そして、われわれの前にいま新たなスタイリストが現れた。ノリ・ケンゾウ、現在は乘金顕斗に改名したいっぷう変わったこの書き手が差しだすのは新たな文体である。オブジェのような文、そしてその文で呈示される奇妙なミニマリズム。
収録作品は三作。「対岸にいる男」は大学時代の友人からバーベキューに誘われた男が陥る奇妙な状況、「入園料」はどことも何ともつかない「園」で、チケットを売る男とそこにやってきた女の一幕物の芝居のようなやりとり、最終電車からはじまり、おそらく誰もが予測不能の展開を見せる脱力的な傑作「ファイト」。
すべてが意味に満たされ、けれどけっして意味では捉えがたい一人称の世界。新しい作家の登場である。
400字詰め原稿用紙換算約105枚。表紙はすずの木。
価格500円。
対岸にいる男 抜粋
そうしてしばらくの間、肉を焼き、肉を配り、肉を食らい、そして酒も飲んだ。アルコールが周り、少し酔い始めると、自然と周りのものと会話もできるようになった。しかしそれでもまだ、私の名前を呼ぶものはいなかった。特別珍しい苗字ではないのだが、どうしてなのだろう。もしくは特別珍しい苗字ではなかったのがよくなかったのか。まあいいのだけれど、でも本当に忘れてしまったのか、という疑念は残る。あるいは、ただ名前を口にする機会がないだけ、とかそういうことだろうか。分からないが、そんなことを考えてないで、ねえ、俺の名前、覚えてる? という一言を発せばよいのに私はそれができない。たったそれだけのことが言えないまま、一心不乱に肉を焼き続けているうちに、小便がしたくなった。しかし私はこういう河川敷などに設置されている仮設トイレが苦手なので、バーベキュー場から少し離れた河川沿いまで、酔い醒ましもかねてふらふらと歩いていき、草むらで隠れて立ち小便をすることにした。そこでズボンのチャックに手をかけ下ろそうとしたときに、ふいに見上げた先に見えた対岸にいる、見知らぬ男と目が合ってしまったのだった。
目が合った瞬間、男は私に向って両手を大きく振りながら何かを大声で叫んだ。しかしその声がまったくと言っていいほど対岸にいる私には届かない。たしかに大声を発しているように見えたのだが、私の勘違いだろうか。しかしながら立ち小便をしようとしていたところを見られた恥ずかしさもあり無視はできず、私は慌ててチャックにかけていた手を止めた。それから、
「なんですかー?」
と、大声で呼びかけてみると、男がまた何かを叫んだ……ように見えるのだが、やはり誰かが叫んだ声などはどこからも響いてこない。辺りはただ川の流れる音と、水面 を泳ぐカモの鳴き声がぐわっぐわっと聞こえるくらいの静けさがあるのみだった。
入園料 抜粋
だから本音を言ってしまえば、それこそ誰一人としてこの園に来ないのが一番よい。給料は時給制なので人が来ようが来なかろうが私の賃金は変わらない。だったら誰も来ないほうがいいに決まっている。人がまったく来なくて困るとするなら、人がまったく来ないせいでここが廃園に追い込まれればまた私が無職になってしまうということぐらいだろう。むしろ廃園になるならなってくれてもいい。廃園という不可抗力の末の無職であれば、私の責任はないのだから、誰にも非難されずにまた無職の生活が送れるというものだ。といったことを考えているところに聞こえてきたのがこの女の声だった。
「ひとくちに入園料と言っても色々あるでしょう? だって。大人とか子供とか、あとシニアだとかなんとかだとか色々」
「え、あの、シニア、ですか?」
「誰がシニアよ。シニアだけじゃなくて、子供とか大人とか、色々よ」
女は、私が女の容姿を見て、あなたはシニアなのかと伺いをたてていると思ったのか、かなりいらついた様子だった。
「いえ、その、お客様がどうというのじゃなくて、何の話なのかと……」
「話ってなによ」
「あのその、それはさっきお客様が仰っていた内容、と言いますか」
「なに。だからそれは、入園料よ。にゅ、う、え、ん、りょ、う」
「にゅうえん、りょう……ですか」
ファイト 抜粋
てめえこのやろう、と叫ぶ上司の顔を見ながら、彼は心底言われていることの意味が分からないという目で上司を見ていた。てめえこら、お前が休んでる間にどれだけあいつらが苦しんでたか分かってんのかぼけ。と上司が言って私たちの座るデスクの方の、誰でもない曖昧な空間を指さした。お前こそどれだけきつかったか把握すらしてないだろうが。という言葉がすぐさま浮かんできたが口には出さず、目を凝らしてパソコンの画面 を見るそぶりをしてキーボードをぽつぽつと叩いて、あまり凝視はしないよう横目で彼らを見ていた。
激怒されながら、先輩社員は上司の顔を見ずに何度か頷いて、ときおり手のひらで首の後ろを掴み、凝り固まった首の筋肉をほぐすように傾げたり、眠たい目をこする仕草で目やにを取ったりしていた。その、いやに堂々としてリラックスした彼の態度に納得のいかない上司はさらに声を張り上げ、もう何を言っているのかも分からないくらい激高していた。少し離れた位 置にいる私の距離でも耳を塞ぎたくなるくらいの煩さなのだが、先輩社員は意に介せずで、以前までの、怒られれば虚ろな目をして、ぺこぺこと頭を下げて謝ってその場を凌ぐことだけを最優先にし、自身の感情を押し殺しているように見えた彼はどこにもいなくなっていた。休んでいる間に何があったのかは知らない。何か重大な事故にあったようだ、というのはその前の週の朝礼で聞いていたが、見たところ彼の体には目立った外傷のようなものは見当たらない。けれども彼のその清々しいほどに気の抜けた態度は痛快でもあった。上司が右といえば右になる、それに従うほかない職場において、微かなる反抗を見せる先輩社員の姿が、私には気分がよいものだった。