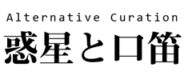第12回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作品。書き下ろしの前日談「サンメダール教会の奇跡」併録。
斉藤直子はさまざまな意味で稀な作家である。その事実はデビュー作である本作からして明白である。ユーモア、ストーリーテリング、軽重を同時に感得させるテイスト。全貌はまだ知れず、おそらくそれは誰もが驚くような壮大なものではないだろうか。
日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞の本作は、十八世紀半ばのパリやヴェネツィアを舞台に、女装の騎士デオンが活躍する歴史ファンタジーあるいは錬金術ファンタジーで、おそらく類書のない小説である。
登場するのは関西弁を話すカザノバ、最愛王ルイ十五世とその愛人ポンパドゥール夫人、不死と噂されるサン・ジェルマン伯爵、催眠術の創始者フランツ・アントン・メスメルなど。豪奢で絢爛として、幻想文学の核に根ざし、かつユーモア小説でもあるという稀有の作品である。
「サンメダール教会の奇跡」は最愛王ルイ十五世とのちのコンティ親王の少年時代の一逸話である。こちらは、シリアスな作品で、ルイ十五世の怪物めいた性格が重厚に活写され、この作家の筆力が並々ならないものであることを証している。
400字詰め原稿用紙換算約310枚。「サンメダール教会の奇跡」は約50枚。
大森望の紹介つき。
価格380円。
仮想の騎士 抜粋
ジャック・カザノヴァは不機嫌だった。
中世スペインのドン・ファンとともに、艶福家の代名詞のごとく後世に語られることになる彼だが、このころ艶も福も不調なことこの上ない。
諸々の不運の先陣を切って彼に襲いかかったのは、生涯最大の失恋だった。恋多き男[アヴァンチュリエ]と恋多き女[アヴァンチュリエール]の激しい恋の結果 である。女は、眠るカザノヴァをベッドに残し、ある朝唐突に消えた。さよならの言葉は、あろうことか窓ガラスに彫られていた。カザノヴァが贈ったダイヤモンドの指輪で刻んだのである。そんな劇的な女であった。
「――もうええっちゅうに」
カザノヴァは、思い出したくもない記憶を勝手に再生し始めた頭をがしゃがしゃと掻き毟った。
ベッドサイドの時計を見ると、八時であった。こんな早くに目覚めてしまうのもまたついてない。朝は庶民の時間である。彼が渡り歩いている社会は、午後から一日が始まるのだ。本来夜行性ではない人間には甚だ不健康なその社会は、|貴族社会[ノブレス]という。そこには平民の税金で暮らす特権階級者たちが棲息する。平民であるカザノヴァは、彼等に搾取された税金を、話術と演技力で取り返すことを生業としていた。といえば聞こえはいいが、要するに、ぺてん師であった。相手が女性の場合は、業種名がジゴロに変わる。
サンメダール教会の奇跡 抜粋
見開いた少年の目に飛び込んできたものは、互いを墓石に打ち付け合う若い娘たちだった。髪を掴んで回し投げ、服も引き裂く激しい肉弾戦である。裾はめくれて脚の付け根まで剥き出され、こぼれた乳房は墓石に削られ血の玉 を散らせつつ弾む。
「血を捧げよ!」
観客のひとりが拳を上げ、
「おおお!」
十重二十重に巻く人垣も、地鳴りのごとくどよめいた。
からみあう娘らの頬は薔薇色に染まり裸身は大きく波を打ち、やがて導波するごとく揃って痙攣した。恍惚の表情で娘らは上体を仰け反らせ、何かを迎え入れるかのように伸ばした両手を天に向ける。
「来た!」
観衆はみな昂奮にうち震えながら十字を切っている。感極まって自らも墓石に体当たりする者もいた。猛って周囲に躍り掛かる者もあり、乱闘の波頭が随所で突沸した。脱ぎ捨てられた衣服と血飛沫が宙を舞い、肉と肉とがぱあんとぶつかる高音と、どさりと地に叩きつけられる低音が入り乱れる。間隙に発つのは悲鳴ではなく歓声だ。見れば墓石や敷石には、新旧の血糊が赫く黒くこびりつき、失禁や体液の跡も異臭とともに生々しい。おそるべきことにその汚泥をありがたげに手に取る者、身体に塗りたくる者すら見受けられる。開いた口へと運びかけた者もいたが、顔をそむけた少年には、その後の成り行きはわからなかった。
(……あっ)
そむけた先に、さきほどの肩車の男児がいた。
小さな男児は同じく小柄な父により、足に汚泥を塗られていた。
その足は湾曲し、おそろしく細い。男児もまた目の先に少年を見つけ、小粋に目くばせした。
「これでおいらも歩けるようになるんだぜ!」
斉藤直子(さいとう・なおこ)
新潟県長岡市生まれ。立教大学文学部心理学科卒業。2000年『仮想の騎士』で第12回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞。