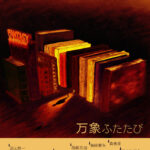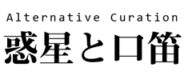日本の小説の世界は広い。しかしもしかしたら逆に見えるだろうか。大量消費が念頭におかれた小説、ドグマ的文学観の下にある作品ばかりと見えるだろうか。いやいや、シーンというものがそれほど単純であることは有り得ない。固有の修辞力と経験と感覚をそなえた作家たちは、顕在化されていないが、マグマのようにつねに足元で噴出を待っているのだ。そのひとりがこの相川英輔である。
相川英輔は幾つかの角度を身につけている。はじめての作品集『ハイキング』で主体となるのは「リーダビリティー」と「奇想」である。堅実で淡々とした文体、遠景のように描かれる登場人物たち、日常を浸食していくストレンジネス。
ゆっくりと徒歩でやってきた作家が描くのは、すこし影の多い世界である。そこを訪れるあなたもおそらくすでにひとつの影である。
短篇4作収録。400詰原稿用紙換算約260枚。表紙はこた。
価格600円。
収録作品紹介
ハイキング
明かりをつけるとテーブルに夫がいた。レトルトの焼きそばが唇からこぼれ出ている。祥子は立ちすくむ。食パン、冷凍チャーハン、実家から送られてきたハムのセット。テーブルの上にはさまざまな食べ物の袋が散乱していた。リンゴの芯まで転がっている。いろいろな物が混ざり合わさった、むっとするような臭いが室内に充満している。
妊娠中の若い妻はひとりで夫の帰りを待っている。ようやく会社の同僚たちとのハイキングから帰ってきた夫の振る舞いは、どこか異常だった。
日常の何気ない出来事を通じて呼びかけてくる異質な世界からの声。ハイキングに行った先でいったい何があったのか? 新しい感触のスーパーナチュラルテール。
日曜日の翌日はいつも
一週間が過ぎ、また「あの日」がやってきた。
日曜日のつぎの日にオリンピック候補の水泳選手に起こったことは、実力が遥か上のライバルたちを追いこす可能性が秘められていた。
第13回坊っちゃん文学賞佳作作品。
ファンファーレ
月光の下、草むらを鶏とおっさんが走り回っていた。鶏たちは飛び立とうと思い思いの方向に駆け、羽を広げるが、五センチも浮くことができていない。まるでライト兄弟の飛行実験のようだ。「飛べ、飛べ」とおっさんは鶏たちを追い立て、手本を見せるように自分もぴょんぴょん跳ねている。
昼の光が絶望的な疫病をもたらし、世界中の人々は昼は眠り、夜のあいだに生活を営むようになった。昼の時代を知らない二人の若者、堤と富士は巨大な養鶏場で働いている。無能でただ嫌悪すべき存在であるように見える先輩中倉、二人から陰でおっさんと呼ばれている彼の趣味は、ドッグレースで賭けることだった。夜の世界、夜のドッグレース、ユースと疫病と夜のファンファーレ。
打棒日和
スイングを繰り返すうちにだんだんミートできるようになってきた。よかった。あのときの手応えはまだ残っている。ボールを捉えだすと健三さんの口数も減ってきた。よし、こうなったら健三さんが何も言い返せなくなるようなバッティングをしてやろう。私は打ち終わると、無言でもう一度プレイボタンを押した。
「まゆ」は図書館でアルバイトとして働いている。高卒で、司書補の資格をとるために通 信教育で勉強している。とりたてて見るべきところのないまゆには趣味がひとつあった。バッティングセンターでボールを打つことである。まゆは野球がしたいわけではなかった。ただバッティングセンターでボールを打つことが好きだったのだ。それは何も生まない趣味である。しかし何も生まないことはほんとうに何も生まないのだろうか。『文學界』2005年4月号掲載。
相川英輔 (あいかわ・えいすけ)
1977年生まれ。2016年福岡市文学賞受賞。
惑星と口笛ブックス配本の『ヒドゥン・オーサーズ』に「引力」を寄稿。『文学ムック たべるのがおそい』vol. 3に「エスケイプ」掲載。
特技は洗濯ものを畳むこと。
福岡市在住。