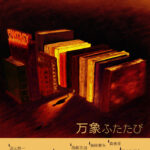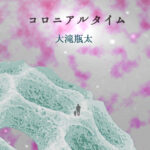バカミスを愛せよ 猫を愛せよ
倉阪鬼一郎が持つ多くの顔のなかでも〈ミステリ作家〉は自身にとって重要なようで、なかでも〈バカミス〉への愛は深い。
本作はバカミスと抒情と猫の混合体である。作家漆原俊作の噴飯物の文章に憤り、謎解きに驚き、そしてしみじみとしてほしい。
表紙の絵は作者。400字詰め原稿用紙換算約51枚。350円
プロフィール
倉阪鬼一郎
1960年1月28日、三重県上野市(現・伊賀市)生まれ。早稲田大学第一文学部文芸専修卒。同大学院文学研究科日本文学専攻中退。
在学中に幻想文学会に参加、1987年、短篇集『地底の鰐、天上の蛇』でデビュー。印刷会社、校閲プロダクション勤務を経て、1998年より専業作家。ホラー、ミステリー、幻想小説、近年は時代小説を多数発表、オリジナル著書数は240冊を超える。俳句、短歌、散文詩の短詩型文学、翻訳、油絵、作曲なども手がける。他の著書に『倉阪鬼一郎散文詩集成』など。
りこくん抜粋
(前略)
もう擦り切れた夢。黄旧館はここで滅びた。ばったりと倒れて死んだおとこのむくろが館に転がり、闇が包む。屍体はここにはない。立ち去り消えた犯人が屍体をここから消した。あたりは闇だ。滅びた館をこの街の闇が包む。ありえたかもしれないこころの闇だ。
死とありふれた犯罪。
死がこの街の館を覆う。かりそめの二つの館、そこの住人の片割れが去り、犯人が残った。ここ六本木の狭隘な裏通りを、探偵が追う。ここ六本木の有名人であり事件を解決してきたこの男が動く。
りりりと鳴る電話を受けてこの男が動けば、当たり前のように事件はここで解決されるのであり、それが運命だ。そこに潜む犯人にばったり出くわしても動じずこの男は解決に導く。りそうの結末。
まあこの事件は、簡明であり、犯人も被害者もここ六本木で生まれてありふれた遺産相続で、この事件となった。ありふれた犯罪。助詞がこの題名に三つも加わり、新たな意味が、ここに付与されれば、かりそめの姿は変わる。この真相は
* *
「これで終わり?」
みはとが何とも言えない顔つきでたずねた。
「一作目の問題文はこれで終わりだよ。あとは短い解決篇だけ」
よく寝ているりこくんをなでながら、翔一が答えた。
「申し訳ないけど……」
みはとは本当に申し訳なさそうな表情で言った。
「翔ちゃんのおじさんが売れなかったのは当然のような気がする」
「そりゃ、まあだれしもがそう思うだろうね」
翔一はあいまいな顔つきで答えた。
「これって、悪いけどプロの作家の文章じゃないと思う。素人さんだとしても相当下手なはず」
と、みはと。
「まあ、それは衆目の一致するところだろう」
翔一は軽くうなずいた。
「とにかく、目がすべっちゃって、テキストが頭に入ってこないのよ」
みはとは頭を指さした。髪型は少し古風なボブテールだ。
「無理もないと思うけど、問題文はこれだけだから」
翔一は申し訳なさそうに言った。
「二つの館が出てきて、どちらでも事件が起きたみたいなんだけど、とにかくその関係がはっきりしなくって。探偵も名無しさんだし」
みはとはお手上げの様子だった。
「たしかに、『この真相は』と言われても当惑するばかりかと」
翔一がそう言ったとき、りこくんが大きなあくびをしてから目をさました。
「おはよう、りこくん」
みはとが声をかける。
「りこくんの飼い主だったおじさんの小説、むずかしいにゃ」
猫は前足であごをかきはじめた。
「おまえはわかってるよな」
翔一が言う。
りこくんは、今度は小さなあくびをした。